「チームの業務フローを改善する、素晴らしいアイデアを思いついた。でも、資料をまとめるのが面倒で、提案するのを先延ばしにしていたら、一ヶ月後、別の部署が、全く同じ改善案を実行して、手柄を全て持っていってしまった…。ああ、『善は急げ』だったのに」 「重い荷物を持って困っているお年寄りを見かけた。『助けてあげようかな』と、一瞬ためらっている隙に、別の人が、さっと手を貸してしまった。良いことをする、チャンスを逃してしまった…」
この、「もっと早く行動しておけばよかった」という、ほろ苦い後悔。それを、昔の人は『善は急げ』という、簡潔で、力強い言葉で、戒めました。
これは、単に「良い人間でありなさい」という、道徳的な教えなのでしょうか?いいえ、それだけではありません。これは、人生というゲームにおける、極めて重要な「勝つ」ための原理を説いた、高度な戦略論なのです。今回は、この「即時行動の原則」を、戦略・ゲーム理論の世界から、クイズ形式で分析していきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
チェスやビジネス、あるいは、実際の戦闘において、先んじて、断固たる行動を起こし、相手を、自分の動きに対応せざるを得ない「受け身」の状態に追い込むプレイヤーは、戦局を、圧倒的有利に進めることができます。
このように、自らが、先に、そして、積極的に行動することで、ゲームの流れを決定づけ、状況をコントロールする、という、戦略における、この決定的に重要な「優位性」のことを、何と呼ぶでしょう?
- ナッシュ均衡
- 主導権
- ゼロサムゲーム
解答と解説
その「好機」を、勝利へと繋げるための、戦略的な概念。見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『主導権』(しゅどうけん) でした!
英語では「Initiative(イニシアチブ)」と呼ばれ、あらゆる競争において、勝利の女神が、どちらに微笑むかを決定づける、最も重要な要素の一つです。
なぜ『主導権』を握ることが、「善は急げ」の本質なのか?
チェスの対局を、想像してみてください。あなたは、盤面を眺める中で、相手の防御陣における、ある致命的な「弱点」を発見しました。この弱点を突く手は、間違いなく「善」手です。
そして、ここで重要なのは、多くの選択肢の中から、この「一兎」に集中することです。 もし、あれもこれもと欲張ってしまうと、どうなるかご存知ですか?
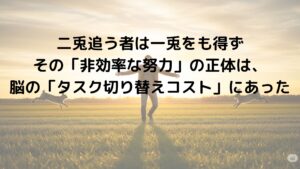
- ケースA:「急がない」場合
あなたは、こう考えます。「この手は、後でも指せる。まずは、別の駒を、ゆっくりと展開しよう」。しかし、あなたが、他の、悠長な手を指している間に、相手もまた、同じ弱点に気づき、守りを固めてしまいました。好機は、永遠に失われました。あなたは、主導権を、相手に明け渡してしまったのです。 - ケースB:「善は急げ」を実践した場合
あなたは、好機を見つけた、まさにその瞬間に、間髪入れずに、その「善」手を指します。すると、どうでしょう。今度は、相手が、あなたのその一手に対応せざるを得なくなります。彼は、もはや、自分の立てた計画を実行する余裕を失い、あなたの攻撃を防ぐための、後手後手の「受け身」の戦いを、強いられるのです。あなたは、完全に、ゲームの『主導権』を握ったのです。
「善は急げ」とは、この「主導権を握る」ための、究極の戦略原則なのです。
「善い行い」や「善いアイデア」とは、人生というゲーム盤の上に、突如として現れる、「戦略的な好機」です。そして、その好機の窓は、えてして、非常に短い時間しか、開いていません。人生の「盤面」は、刻一刻と、変化しているからです。
良いアイデアを、思いついた瞬間に実行することで、あなたはその好機を活かし、周囲の世界(あるいは、会社や、他の人々)を、あなたのポジティブなアクションに対応せざるを得ない状況に、引きずり込むことができるのです。
困っている同僚を、すぐに助ける。それは、単に彼を助けるだけでなく、二人の間の、良好な人間関係構築における「主導権」を握る行為です。
良い改善案を、すぐに提案する。それは、単に問題を解決するだけでなく、チームの中で、あなたが、積極的で、価値あるプレイヤーであることを、証明する行為です。
「善いこと」を先延ばしにするのは、戦略的な「大悪手」なのです。なぜなら、それは、自ら、人生の「主導権」を、放棄する行為に、他ならないのですから。
【不正解の選択肢について】
- 1. ナッシュ均衡: これは、どのプレイヤーも、自分だけ戦略を変更する動機がない、という、ゲームの「安定状態」を指します。「主導権」を握る、というのは、この安定を、自分に有利な形に、打ち破るための「動的なアクション」です。
- 3. ゼロサムゲーム: これは、「誰かが勝てば、誰かが負ける」という、奪い合いのゲームのことです。「主導権」の概念は、協力的な(非ゼロサムの)ゲームにおいても、同様に重要です。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: この言葉は、仏教の教えに由来するとも言われています。善い行いをためらわず、速やかに行うことが、悟りへの道を早める、という考え方です。また、ダンテの『神曲』地獄篇にも、「善をなすに遅きは、好機を失う道なり」という一節があり、この知恵が、洋の東西を問わない、普遍的なものであることが分かります。
- 面白雑学: 米空軍のジョン・ボイド大佐によって提唱された、「OODA(ウーダ)ループ」という、有名な意思決定のモデルがあります。これは、「監視(Observe)→情勢判断(Orient)→意思決定(Decide)→行動(Act)」というサイクルを、いかに相手より速く回すかが、勝利の鍵である、という考え方です。相手より速く、このループを回すことで、主導権を握り、相手を、自分がコントロールする、目まぐるしい状況変化への、後手後手の対応に、追い込むことができるのです。「善は急げ」とは、まさに、このOODAループの「行動(Act)」の部分の、スピードの重要性を、強調した言葉と言えるでしょう。
まとめ:明日から使える「知恵」
「善は急げ」とは、単なる道徳的な命令ではありません。それは、戦略論における、基本原則なのです。「善い行い」や「善いアイデア」とは、好機の窓であり、迅速に行動することこそが、その「主導権」を握り、自らのポジティブな影響力を、最大化するための、唯一の鍵なのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『好機とは、はかない優位性である。「善いこと」を実行するための、完璧な瞬間を待つな。それを、即座に実行すること自体が、その瞬間を、完璧にするのだ。主導権を、握れ』ということです。
あなたが、「いつかやろう」と、先延ばしにしている「善いこと」は何ですか?この記事を読んだ後、それを「急ぐ」ための、最初の、具体的な一歩は何でしょうか。
この記事では、「主導権」を握るための、「スピード」の重要性を、解説しました。しかし、常に「急ぐ」ことだけが、正解なのでしょうか? 時には、一見、遠回りに見える、慎重な道を選ぶことこそが、最良の結果に繋がることもあります。「急がば回れ」ということわざが、その、もう一つの、重要な戦略思想を、教えてくれます。
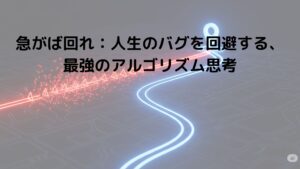
「急ぐ」べきだと頭では分かっていても、つい先延ばしにしてしまう…。その「行動できない」という悩みにも、実は科学的な原因と対策があります。先延ばし癖を克服するための心理学的なアプローチを、こちらの記事で解説しています。
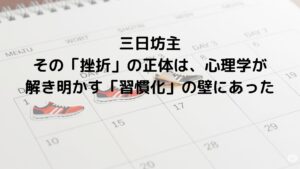
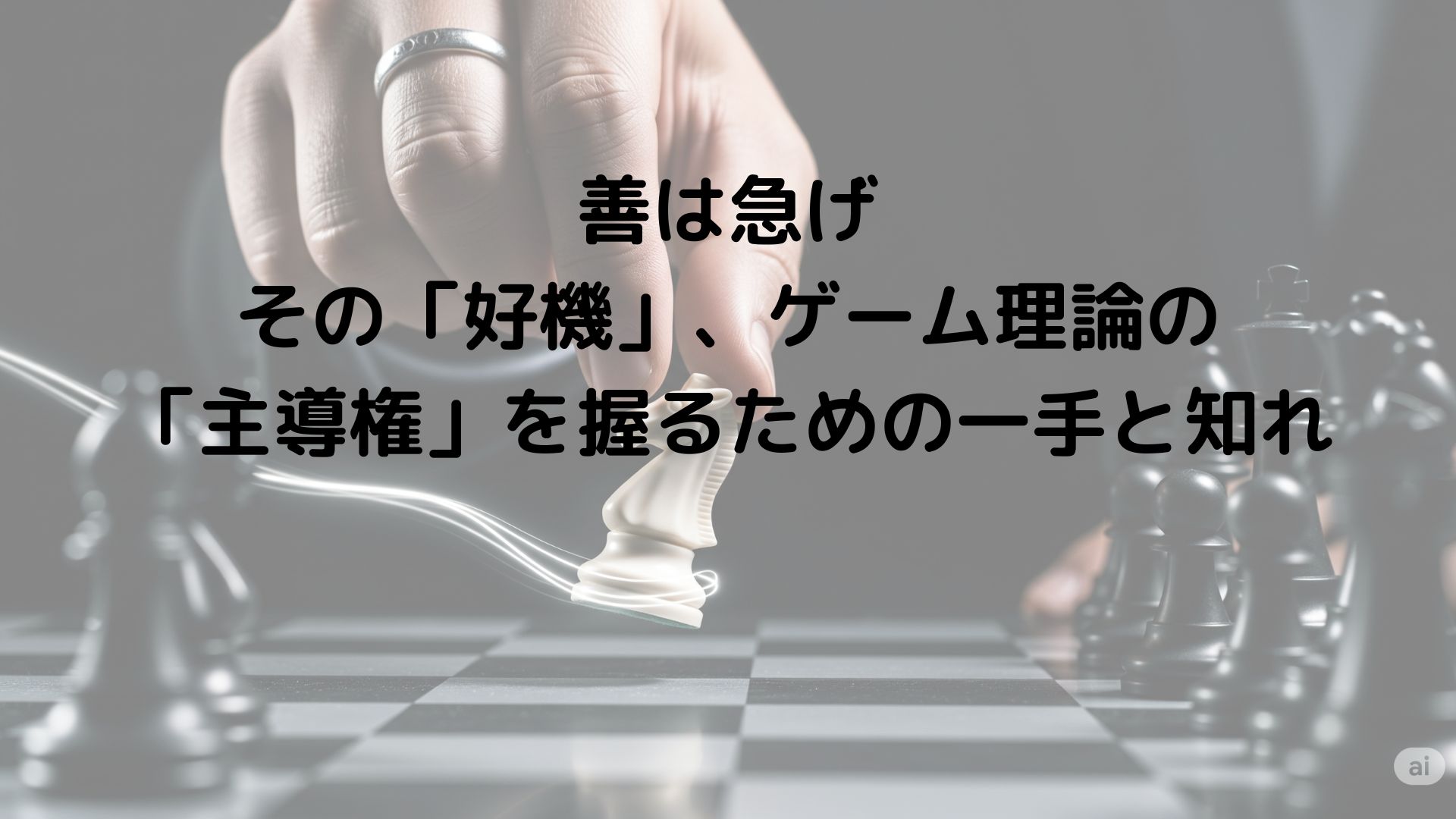
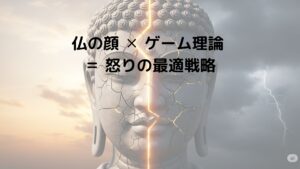
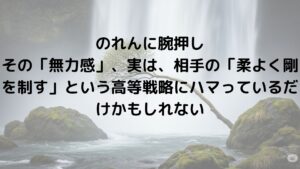
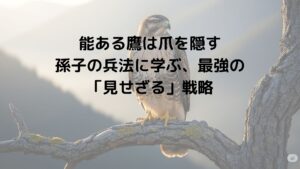
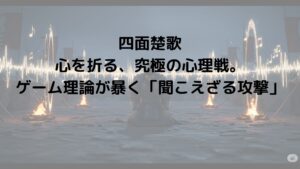
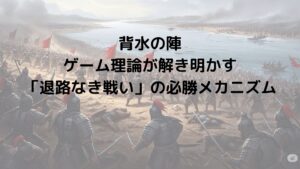
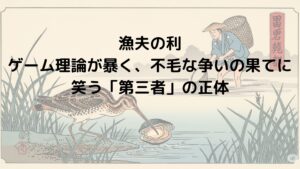
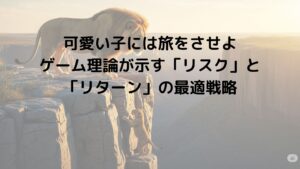
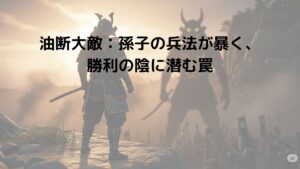
コメント