電車で、うっかり財布を落としてしまった。もう二度と返ってこない、と諦めていたら、見ず知らずの人が拾って、駅に届けてくれていた。中身も、全て無事だった。ああ、本当に、渡る世間に鬼はなし、だなあ…。 海外旅行中、道に迷い、言葉も通じず、途方に暮れていた。すると、地元の方が、自分の時間を30分も割いて、身振り手振りで、ホテルまで案内してくれた。この世も、まだ、捨てたものじゃない。
世の中、冷たくて、意地の悪い人ばかりではない。探せば、必ず、どこかに、温かい心や、救いの手が存在する。この、人間社会への、根源的な信頼と、楽観的な眼差しを、昔の人は『渡る世間に鬼はなし』という、温かい言葉で表現しました。
これは、単に、そうあってほしい、という、道徳的な「きれいごと」なのでしょうか? もし、この「優しさ」や「親切」が、何百万年という、壮大な進化の過程で、私たちの遺伝子に刻み込まれた、極めて合理的な「生存戦略」の、結果だとしたら…?
今回は、このことわざを、自然科学、特に、進化論の視点から、人間の「情け」の、意外な起源に、クイズ形式で迫ります。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
「適者生存」という、厳しい自然淘汰の世界において、自らを犠牲にして、他者を助ける「利他的な行動」は、一見、非常に、不合理に見えます。
しかし、進化生物学では、この「利他的な行動」が、なぜ、多くの生物種で、見られるのかを説明する、いくつかの理論があります。その一つは、血の繋がった親族を助けることで、自分と共通の遺伝子を、後世に残す、というものです(血縁選択)。
では、血の繋がりのない「他人」を助ける、という行動は、どう説明されるのでしょうか。「今日は、私が、あなたを助ける。そうすれば、明日は、あなたが、私を助けてくれるかもしれない」という、暗黙の「お互い様」の期待に基づいて、協力関係を築く、という、この、高度な利他的行動を、何と呼ぶでしょう?
- 突然変異
- 血縁選択
- 互恵的利他主義
解答と解説
その「見返りを求めない優しさ」の、本当の理由。その正体を見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 3. の『互恵的利他主義』(ごけいてきりたしゅぎ) でした!
英語では “Reciprocal Altruism” と呼ばれ、人間社会における、協力関係の、進化的な基盤を説明する、非常に重要な理論です。
なぜ『互恵的利他主義』が、「鬼はなし」の、科学的な証明なのか?
何十万年も前の、アフリカのサバンナで暮らす、私たちの、遠い祖先を、想像してみてください。そこでの生活は、常に、死と隣り合わせの、過酷なものでした。
ある日、狩人のAさんは、大きな獲物を仕留め、自分一人では、到底、食べきれないほどの肉を、手にしました。一方、狩人のBさんは、その日の狩りに失敗し、お腹を空かせています。
短期的な、自己の利益だけを考えれば、Aさんは、全ての肉を、独り占めするべきです。しかし、彼は、Bさんに、その肉を、気前よく、分け与えました。これが、「情け」です。
この行為こそ、『互恵的利他主義』の、始まりです。Aさんは、「今日、私がBさんを助ければ、来週、私が狩りに失敗した時には、Bさんが、私を助けてくれるだろう」という、無意識の、そして、進化的にプログラムされた「期待」に基づいて、行動しているのです。
さて、どちらの集団が、より、生き残る確率が高いでしょうか?
A)自分の獲物は、決して、誰にも分け与えない、自己中心的な「鬼」ばかりの集団。
B)お互いに、食料を分け与え、助け合う、「情け」のある人々の集団。
答えは、明らかです。協力し合う、Bの集団の方が、飢饉や、病気、怪我といった、様々なリスクに対して、遥かに、強く、しなやかな、社会的なセーフティネットを、持つことができます。
長い、長い、進化の歴史の中で、「鬼」の集団は、淘汰され、「情け」の集団が、生き残ってきた。私たち、現代人は、その、「協力」という、偉大な生存戦略を発明した、賢い類人猿の、末裔なのです。
一方で、人生というゲームには、「協力」だけでなく、「競争」の側面も、確かに存在します。 いち早く行動し、「主導権」を握ることが、勝利に繋がる、という、もう一つの戦略原理については、こちらの記事で詳しく解説しています。
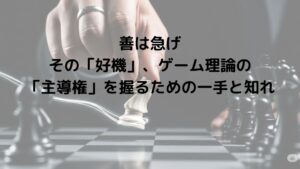
「渡る世間に鬼はなし」とは、この、進化の、大いなる結論を、肯定する、民俗学的な知恵なのです。私たちが、見ず知らずの他人に対して、優しさや、親切心を感じるのは、それが、道徳的に「正しい」から、というだけではありません。それは、「協力し合うことこそが、最も、生き残る確率の高い、優れた戦略である」と、私たちの遺伝子が、知っているからなのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 突然変異: これは、遺伝子が、偶然、変化することです。利他的な行動という、複雑な「戦略」そのものを指す言葉ではありません。
- 2. 血縁選択: これは、自分の子どもや、兄弟といった、血縁者を、助ける行動を、説明する理論です。「他人」への親切を説明するには、「互恵的利他主義」の考え方が、必要となります。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 江戸時代の浄瑠璃や、浮世草子の中に、その用例が見られる、古くからの、日本のことわざです。平和な時代が続き、人々の交流が活発になる中で、世の中も、捨てたものではない、という、人間社会への、楽観的な信頼感が、育まれていった背景があるのかもしれません。
- 面白雑学: 行動経済学には、「最後通牒ゲーム」という、有名な実験があります。
プレイヤーAは、1万円を与えられ、その分け前を、プレイヤーBに、提案します。もし、Bが、その提案を受け入れれば、二人とも、提案通りの金額をもらえます。しかし、もし、Bが、その提案を「不公平だ」として、拒否すれば、二人とも、1円も、もらえません。
もし、人間が、完全に合理的な「鬼(経済人)」であれば、Aは、Bに「100円だけやる」と提案し、Bは、「ゼロよりはマシだ」と、それを受け入れるはずです。しかし、実際には、このような、あまりに不公平な提案は、Bによって、ほとんどの場合、拒否されます。Bは、自らの利益を犠牲にしてでも、「自己中心的な、鬼の振る舞い」を、罰しようとするのです。これもまた、私たちが、いかに、「公平さ」や「協力」を重んじるように、進化してきたかを示す、面白い証拠です。
まとめ:明日から使える「知恵」
「渡る世間に鬼はなし」とは、単なる、甘い、楽観論ではありません。それは、進化生物学が裏付ける、科学的な真理でもあるのです。「利他主義」や「親切」は、単なる美徳ではなく、協力的な集団が、自己中心的な集団に、打ち勝ってきた、という、何百万年にもわたる、生存競争の末に、私たちが獲得した、偉大な「生存戦略」なのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『あなたが見知らぬ人から受け取る、その優しさは、決して、気まぐれな奇跡ではない。それは、あなたの祖先たちが、結んだ、何百万年もの、生存のための、相互扶助の契約の、こだまなのだ。それを信じ、そして、あなたもまた、その契約の、一員であれ』ということです。
あなたが、最近、「渡る世間に鬼はなし」と、心から感じたのは、どんな時でしたか?
この記事では、なぜ、私たちの世界が「鬼のいない」協力的な社会として、成り立っているのかを、進化論から、解説しました。しかし、歴史上、この「性善説」が、全く通用しない、本当の「鬼」を前にして、大いなる悲劇を生んだことも、また、事実です。その、厳しい現実を、「馬の耳に念仏」ということわざを通して、探求したのが、こちらの記事です。
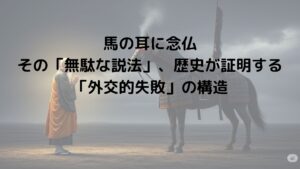
この記事では、協力関係が、いかに、優れた生存戦略であるかを、解説しました。では、その協力関係を、裏切り者から守り、維持するための、具体的な「行動ルール」とは、何でしょうか? 「仏の顔も三度まで」ということわざが、その、驚くほど、シンプルで、強力な答えを、教えてくれます。
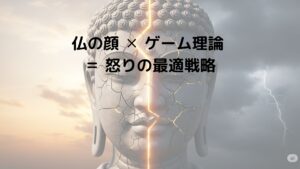
この記事では、「なぜ」私たちが、協力的な社会を築いてきたのか、その「進化的戦略」を、解説しました。では、その「協力」や「共感」を、可能にしている、私たちの脳の、具体的な「神経的な仕組み」とは、一体、どのようなものなのでしょうか? 「鬼の目にも涙」ということわざが、その驚くべき秘密を、教えてくれます。
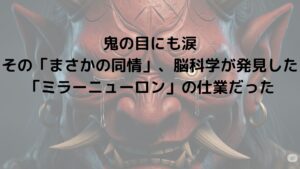
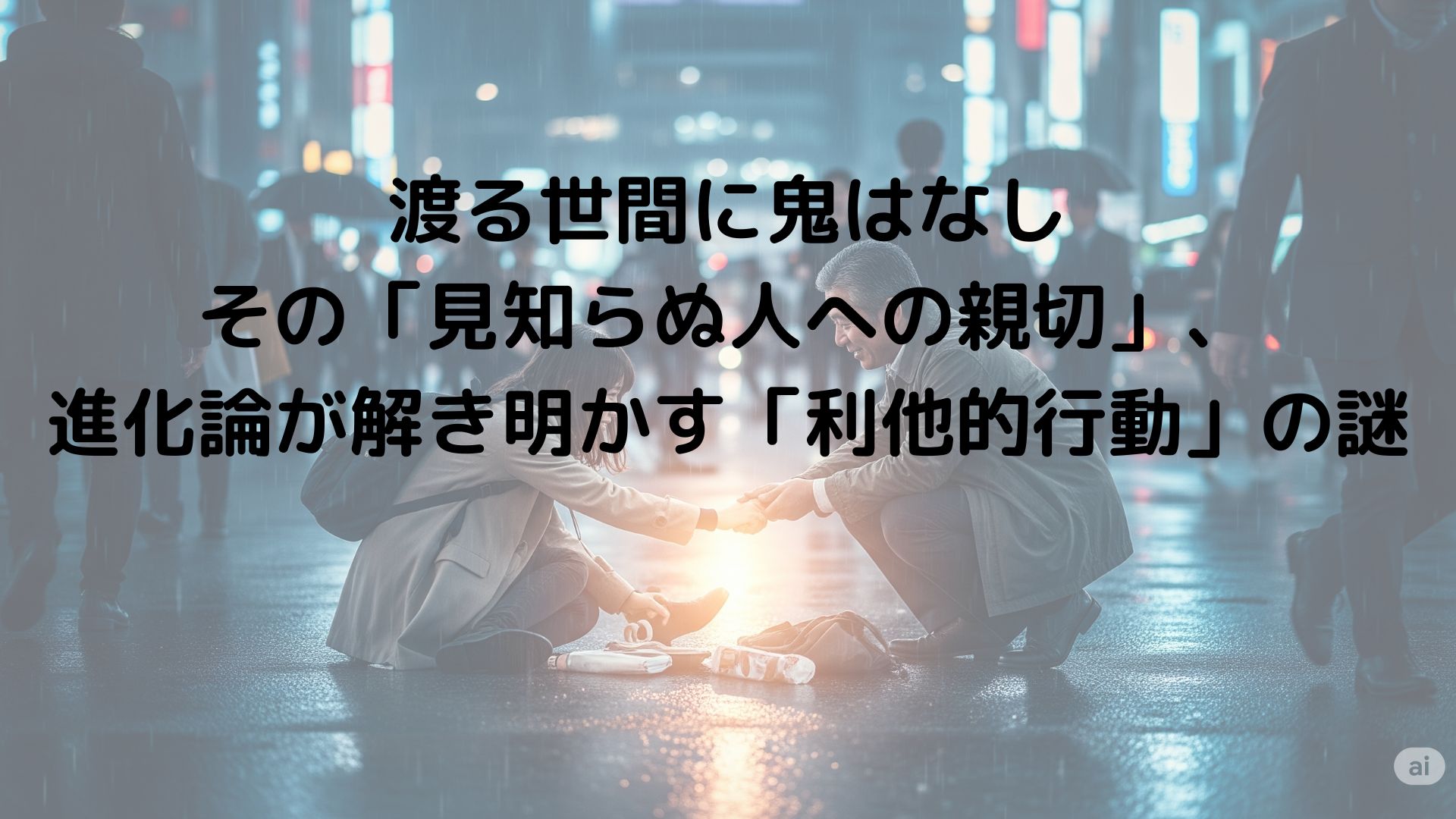
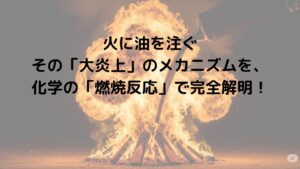
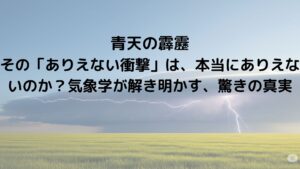
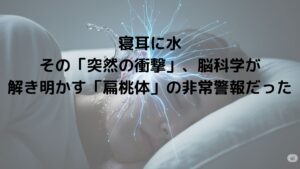
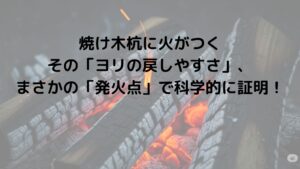
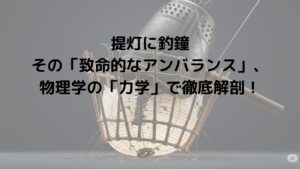
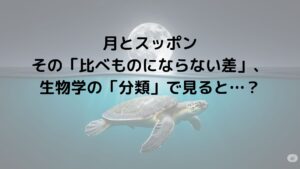
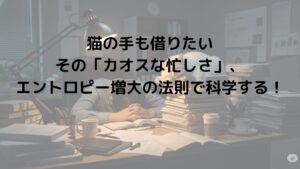
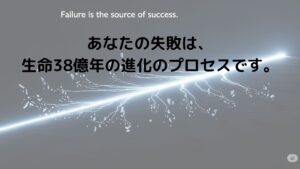
コメント