彼は、我が社が誇る、天才プログラマーだ。しかし、先週、彼が書いたコードが原因で、システムに重大なバグが発生した。まさに「猿も木から落ちる」だな…。 彼女は、オリンピックで3連覇を果たした、絶対女王。しかし、最後の大会で、彼女は、まさかの初歩的なミスで、メダルを逃してしまった。どんな達人でも、失敗はするのだ。「猿も木から落ちる」とは、よく言ったものだ。
その道の達人や専門家であっても、時には、信じられないような失敗をすることがある。この、万物に共通する「完璧ではない」という真理を、私たちは『猿も木から落ちる』ということわざで表現します。
私たちは、この現象を、単なる「珍しい事故」や「気の緩み」として片付けてしまいがちです。しかし、もし、この「達人の失敗」が、現代の巨大なコンピュータシステムにおいては、「起こるべくして起こる、必然的な出来事」として、あらかじめ計算に入れられているとしたら…?
今回はこのことわざを、情報科学という、極めて現代的な視点から、クイズ形式で分析していきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
Googleの検索エンジンや、Amazonのクラウドサービスのような、巨大なコンピュータシステム。それを構成する、何万台ものサーバーや、何億行ものプログラムといった、個々の部品は、いつか必ず、故障したり、エラーを起こしたりします。
そこで、現代のシステム設計では、「個々の部品が、絶対に壊れないこと」を目指すのではありません。むしろ、「いくつかの部品が故障することを前提として、それでも、システム全体としては、何事もなかったかのように動き続ける」ように、システムを設計します。
このように、システムの一部に障害(Fault)が発生しても、それを許容(Tolerate)し、全体の機能を維持し続ける、という設計思想や、その性質のことを、情報科学の世界では何と呼ぶでしょう?
- UI/UXデザイン
- フォールトトレランス
- 暗号化
解答と解説
その「達人の失敗」の裏にある、システムの真実。見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『フォールトトレランス』 でした!
日本語では「耐障害性」と訳され、現代の、止まることが許されない、あらゆるITシステムの、根幹をなす設計思想です。
なぜ『フォールトトレランス』が、「猿も木から落ちる」の本質を解き明かすのか?
木登りの達人である「猿」を、一つの、非常に複雑で、信頼性の高い、巨大なコンピュータシステムだと考えてみましょう。例えば、Googleの検索エンジンのような存在です。 この「猿」は、木登り(=検索クエリへの応答)が、驚くほど得意です。滅多なことでは、木から落ちる(=サービスが停止する)ことはありません。私たちは、その存在を、完璧で、決して失敗しないものだと、信じきっています。
しかし、ある日突然、そのサービスが、10分間、停止してしまいました。「猿が、木から落ちた」のです。あれほど完璧だったシステムに、一体何が起きたのでしょうか?
情報科学は、私たちに教えてくれます。どんなに複雑で、精巧なシステムも、何万、何百万という、小さな部品の集合体である、と。そして、たとえ、個々の部品の信頼性が99.999%であったとしても、そのうちのどれか一つが、いつか、必ず故障する確率は、ほぼ100%なのです。つまり、「猿は、いつか、必ず木から落ちる」ことは、統計的に、運命付けられているのです。
だからこそ、現代のエンジニアたちは、「猿が、絶対に落ちない」ことを目指しません。その代わり、彼らは、「猿が落ちることを前提とした、安全ネット」を、あらかじめ設計しておくのです。これが『フォールトトレランス』です。
もし、システムの一つのサーバー(=猿の右手)が故障しても、瞬時に、別のサーバー(=猿の左手)が、その処理を引き継ぐ。もし、一つのデータセンター(=猿が登っている木)が、災害で停止しても、別の国のデータセンターが、何事もなかったかのように、サービスを継続する。
ことわざ「猿も木から落ちる」とは、このシステムの「可謬性(かびゅうせい)」、すなわち、「間違いうる」という、本質的な性質を、見事に言い当てた言葉なのです。どんな達人も、どんなシステムも、完璧ではありえない。失敗は、避けられない。
情報科学が、この古いことわざに付け加える、現代的な教訓は、「だからこそ、失敗することを前提とした、しなやかで、回復力のあるシステムを、あらかじめ築いておけ」ということなのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. UI/UXデザイン: これは、システムを、人間にとって、いかに「使いやすく」設計するか、という思想です。システムの内部的な信頼性とは、直接関係ありません。
- 3. 暗号化: これは、情報をコード化して、安全性を高める技術のことです。システムの故障を防ぐものではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 非常に古くから使われている、日本のことわざです。木登りが得意なはずの猿でさえ、時には、木から落ちてしまう、という、ごく自然な観察に基づいています。どんな名人・達人にも、失敗はある、という戒めとして、広く使われてきました。「弘法にも筆の誤り」「河童の川流れ」なども、同じ意味を持つことわざです。
- 面白雑学: 動画配信サービスの巨人、Netflix社には、「カオスエンジニアリング」という、非常にユニークな品質管理手法があります。その象徴が、「Chaos Monkey(カオスモンキー)」と呼ばれる、自社開発のツールです。この「混沌の猿」は、なんと、本番で稼働中の、Netflixのシステムを、意図的に、そして、ランダムに、破壊して回るのです。エンジニアたちは、この「いつ落ちるか分からない猿」の襲来に備え、常に、強靭で、回復力の高い、フォールトトレラントなシステムを、構築し続けることを、強制されるのです。まさに、「猿は木から落ちるものだ」という真理を、自らシステムに組み込んで、究極の安定性を目指している、面白い例ですね。
まとめ:明日から使える「知恵」
「猿も木から落ちる」とは、達人の失敗を、単に「珍しいこと」として驚くための言葉ではありません。それは、情報科学における「システムの可謬性」の原則を示す、普遍的な真理なのです。どんなに複雑で、どんなに優れたシステム(あるいは、人間)も、完璧ではなく、失敗は、必然的に起こりうるのです。重要なのは、その「完璧ではない」という事実を、前提とすることです。
このように、失敗を許容する「しなやかなシステム」の考え方は、私たち自身の生き方にも応用できます。
では、人間が「転んでも必ず起き上がる」ための、物理的に安定した「心の構造」とは、一体どのようなものでしょうか? その答えを、こちらの記事で探求しています。
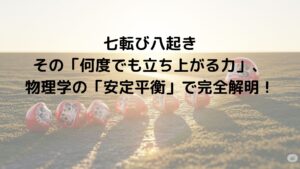
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『達人を、決して失敗しない神として崇めるな。その達人が、いつか来るべき「落下の時」のために、どのような「安全ネット」を張っているかを、学べ。真の熟達とは、決して落ちないことではなく、落ちた後も、生き残るしなやかさにあるのだ』ということです。
あなたが「この人は完璧だ」と思っていた「猿」が、「木から落ちた」瞬間を目撃したことはありますか?
この記事では、失敗が「避けられない」という、システムの、宿命を、解説しました。では、その、避けられない失敗に対して、私たちは、具体的に、何を、すべきなのでしょうか? その、最も、実践的で、効果的な、答えが、「備えあれば憂いなし」ということわざの中に、隠されています。
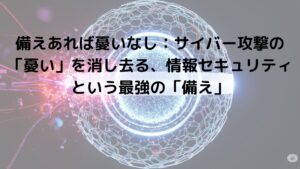
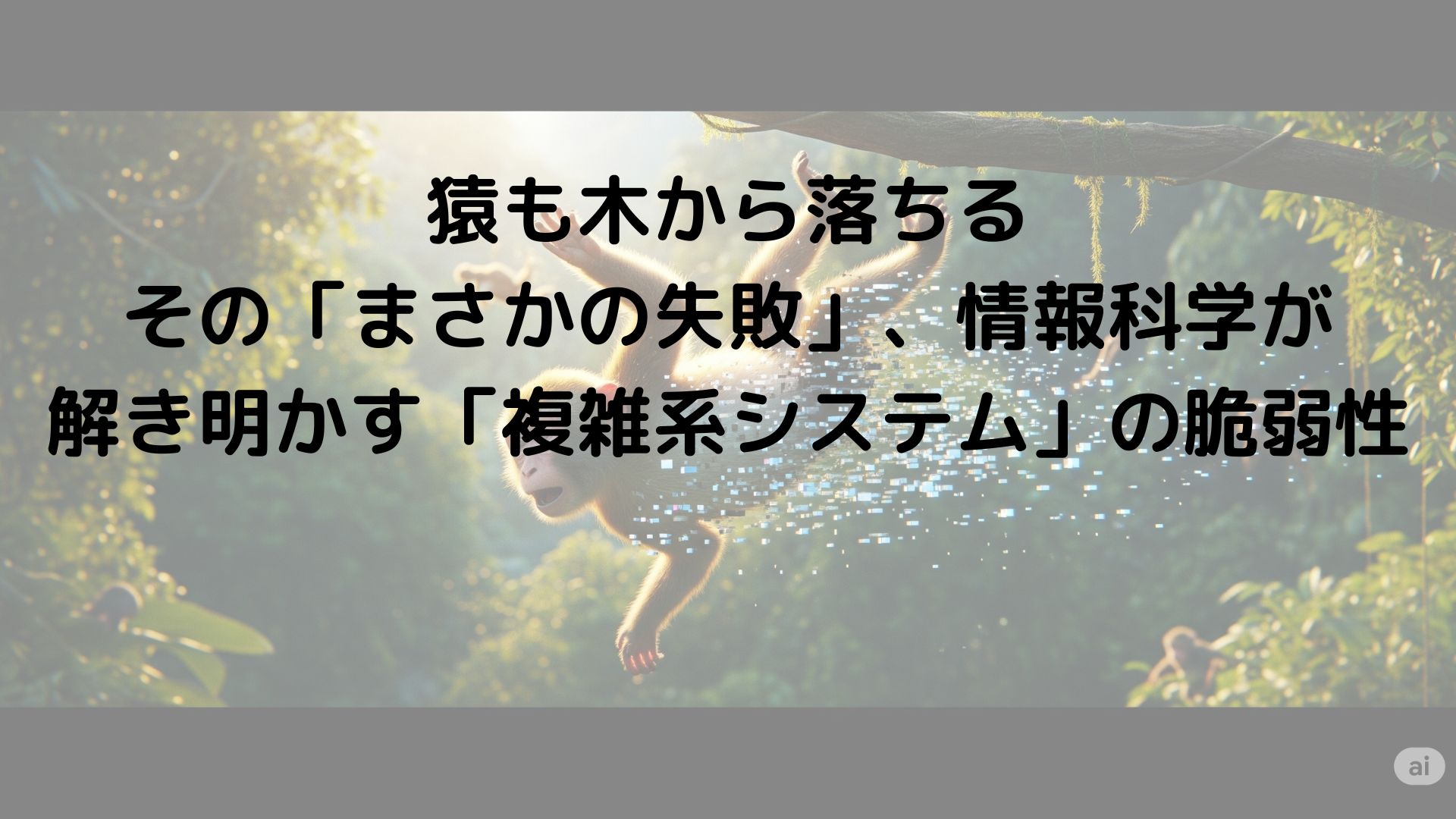
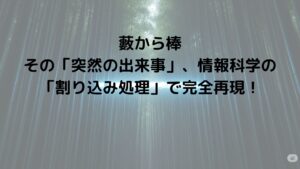
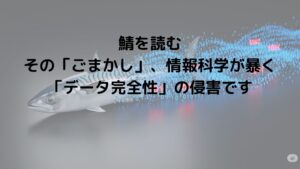
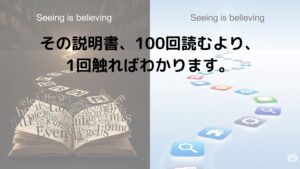
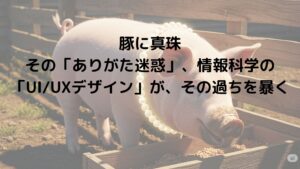
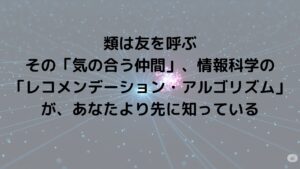
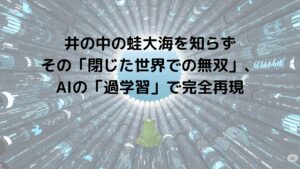
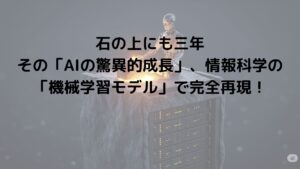
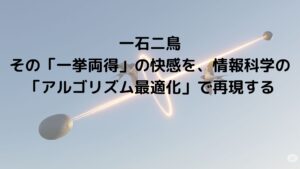
コメント