オンライン会議を聞きながら、同時にメールの返信を打っていたら、会議の重要な決定事項を聞き逃し、メールには恥ずかしい誤字が…。 二つの資格試験に合格しようと、30分ごとに参考書を持ち替えて勉強していたら、結局、どちらの知識も中途半端なまま、本番を迎えてしまった…。
現代社会に生きる私たちは、常に「マルチタスク(複数の作業の同時進行)」を求められ、それができることが、まるで有能さの証であるかのように、錯覚してしまいがちです。
しかし、昔の人は、シンプルなことわざで、その危険性を、私たちに警告していました。それが、『二兎追う者は一兎をも得ず』です。
これは、単なる古い時代の、根性論なのでしょうか?いいえ。その裏には、人間の脳が持つ、根本的な「性能の限界」に関する、動かしがたい科学的な事実が隠されています。今回は、この「マルチタスクの幻想」を、心理学と認知科学の視点から、クイズ形式で暴いていきましょう。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
私たちが「マルチタスク」をしている、と思っている時、実は、私たちの脳は、二つのことを「同時に」処理しているわけではありません。その代わり、脳の「注意」というリソースを、二つのタスク間で、目まぐるしい速さで、行ったり来たりさせているのです。
そして、脳が、一つのタスクから、もう一つのタスクへと注意を切り替えるたびに、僅かな時間のロスと、エラー率の上昇が発生します。この、タスクを切り替える際に、脳が支払わなければならない、認知的な「罰金」や「手数料」のことを、心理学では何と呼ぶでしょう?
- 認知的不協和
- スイッチング・コスト
- コンフォートゾーン
解答と解説
あなたの脳が、毎日支払っている「見えざるコスト」。その正体を見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『スイッチング・コスト』 でした!
この、一回一回は僅かでも、積み重なると、私たちの生産性を、著しく低下させる、厄介なコストです。
なぜ『スイッチング・コスト』が、「二兎」を逃させるのか?
一人の猟師が、野原で、二羽のウサギ(AとB)を見つけたとします。二羽は、それぞれ別の方向へと、逃げていきます。
- 「二兎を追う」という、マルチタスク戦略
猟師は、欲張って、両方を捕まえようとします。まず、ウサギAに向かって、5歩走る。しかし、ウサギBも気になるので、一度立ち止まり、向きを変え、今度は、ウサギBに向かって、5歩走る。しかし、またウサギAが遠ざかるのが気になり、再び、立ち止まり、向きを変え…。
この猟師の、どこが問題なのでしょうか?それは、「立ち止まり、向きを変える」たびに、時間と、前に進む勢いを、失っている点です。これこそが、**『スイッチング・コスト』**です。
彼が、ウサギBを追いかけるために向きを変えている間、ウサギAは、どんどん遠くへ逃げていきます。彼が、ウサギAを追いかけるために向きを戻している間、今度は、ウサギBが遠ざかっていきます。「スイッチング・コスト」を払い続けることで、彼は、どちらのウサギにも、決定的に近づくことができず、最終的に、一羽も捕まえられずに、ただ疲労困憊して、一日を終えるのです。
認知科学は、私たちの脳が、これと全く同じように機能することを、証明しています。私たちが「マルチタスク」と呼んでいるものは、実際には、「高速タスク切り替え(ラピッド・タスクスイッチング)」に過ぎません。
あなたが、メール作成から、オンライン会議へと意識を切り替える時、あなたの脳は、「メールの文面」という文脈を一度メモリから降ろし、「会議の議題」という新しい文脈を、読み込まなければなりません。この切り替えには、時間と、精神的なエネルギーが、必ず必要となるのです。結果として、効率は落ち、どちらのタスクにおいても、ミスを犯す確率が、格段に上がります。
ことわざ「二兎追う者は一兎をも得ず」とは、このスイッチング・コストという、心理学的な原則を、遥か昔に、完璧に見抜いていた、驚くべき生活の知恵なのです。ウサギを捕まえるためには、まず、一羽に狙いを定め、全てのエネルギーを、その一羽に集中させ、「スイッチング・コスト」をゼロにしなければならない。一つの仕事を、質高く、効率的に終わらせるためには、それに「集中」するしかないのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 認知的不協和: これは、心の中に矛盾した考えがある時に感じる、不快感のことです。タスク切り替えの非効率性を説明するものではありません。
- 3. コンフォートゾーン: これは、自分が慣れ親しんだ、心理的な安全地帯のことです。マルチタスクの認知コストとは関係ありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: このことわざは、元々は西洋から来たものだと考えられており、古代ローマの文筆家、プブリリウス・シュルスの言葉にも、類似の表現が見られます。英語の “He who chases two hares catches neither.”(二羽の野ウサギを追う者は、一羽も捕まえられない)という表現も非常に古く、狩猟という、誰にでも分かるシンプルな論理に基づいた、普遍的な知恵と言えます。
- 面白雑学: スタンフォード大学のある研究によれば、驚くべきことに、日常的にマルチタスクを行い、自分はそれが得意だと信じている人ほど、実際には、マルチタスクの能力が低い、という結果が出ています。彼らは、無関係な情報を排除したり、思考を整理したり、効率的にタスクを切り替えたりするのが、むしろ、一つのことに集中するのを好む人よりも、下手だったのです。彼らの脳は、常に「注意散漫」である状態に、訓練されてしまっていた、というわけです。まさに、「二兎を追う者は一兎をも得ず」の、科学的な証明と言えるでしょう。
まとめ:明日から使える「知恵」
「二兎追う者は一兎をも得ず」とは、マルチタスクという「幻想」に対する、時代を超えた警告です。認知科学は、私たちの脳が、複数の複雑なタスクを、同時に処理するようには設計されておらず、代わりに、非効率な「タスク切り替え」を行い、そのたびに「スイッチング・コスト」を支払うことで、全てのタスクのパフォーマンスを低下させていることを、証明しています。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『「集中」とは、現代における、最強の超能力である。誰もが、全てのウサギを追いかけることを求めるこの世界で、ただ一羽を選び、それに全力を注ぐ規律を持つ者こそが、最後には、夕食にありつけるのだ』ということです。
あなたが今、同時に追いかけている「二羽の兎」は何ですか?この記事を読んだ後、まず、どちらの一羽に、集中しようと決めましたか?
この記事では、「二兎を追う」ことの「損失」を解説しました。では逆に、一つのことに集中し、力を加え続けると、どのような「利益」が生まれるのでしょうか? その答えは、物理学における「運動量の法則」が、美しく示してくれます。
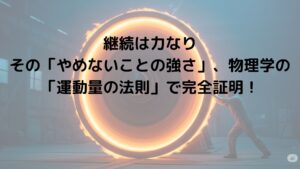
そして、「二兎を追う」マルチタスクが非効率なのは分かった。では、複数の目的を達成したい時、本当に賢いアプローチとは何でしょうか? その答えは、「二兎を追う」のではなく「一つの石で二羽の鳥を落とす」という「最適化」の発想にありました。
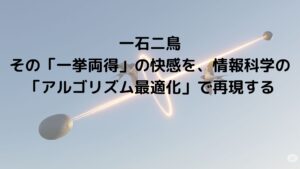
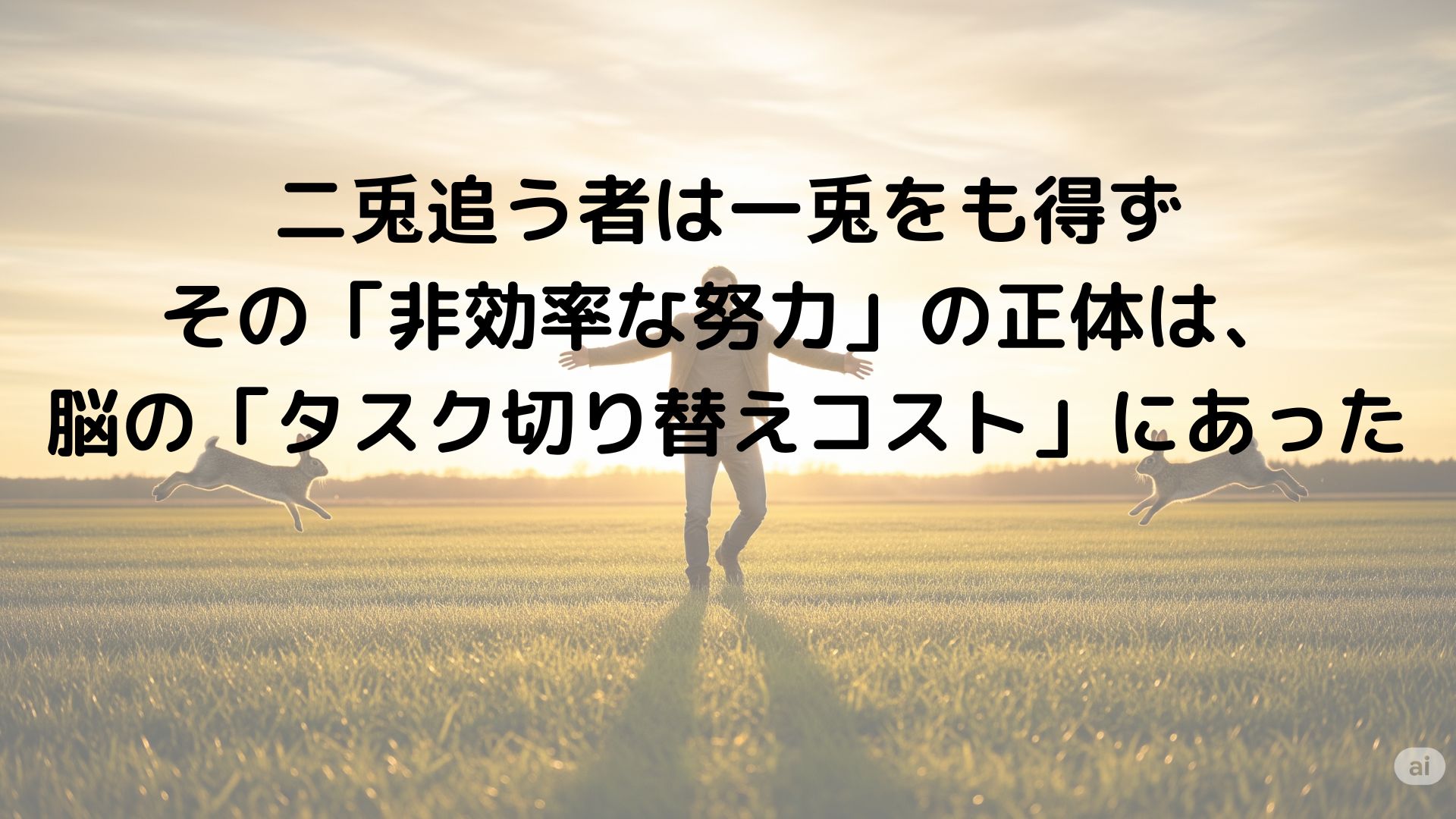
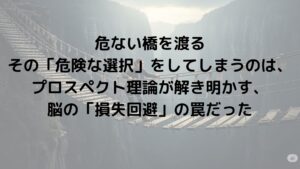
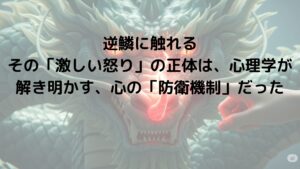
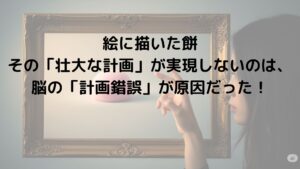
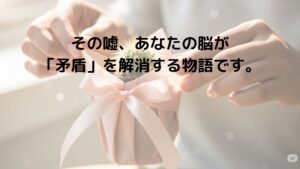
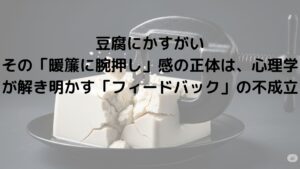
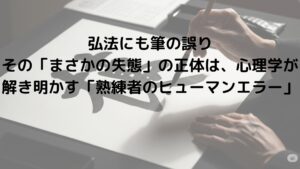
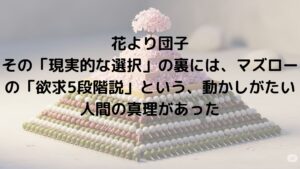
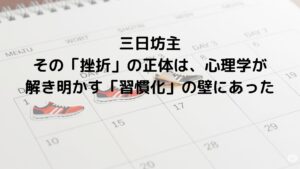
コメント