「うちの祖母に、最新のスマートフォンをプレゼントしたんだ。でも、彼女が使うのは、電話機能だけ。これじゃ、まさに猫に小判だったな…」 「彼に、僕が愛してやまない、難解な現代音楽のレコードを聴かせたんだ。でも、彼は、全く興味なさそうだった。うーん、猫に小判だったか」
価値のあるものを与えても、相手にその価値が分からなければ、全く意味がない。この、ありがた迷惑で、少し切ない状況を、私たちは『猫に小判』と呼びます。
この時、「価値が分からないなんて、猫はなんて愚かなんだ」と、私たちは、つい、受け取り手の側に、問題があるかのように考えてしまいがちです。
しかし、経済学の視点に立てば、問題は、全く別の場所にありました。今回は、このことわざを、社会科学、特に、「価値とは何か?」を問う、経済学の理論から、クイズ形式で探っていきましょう。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
かつての古典派経済学では、物の価値は、それを作るのに、どれだけの労働時間がかかったか、といった、客観的な要因で決まる、と考えられていました(労働価値説)。
しかし、現代の主流な経済学の考え方では、物の価値は、その物自体に、本来的に備わっているわけではない、とされています。その代わり、その価値は、それを受け取る個人が、どれだけそれを「欲しているか」、どれだけの「満足(効用)」を、そこから得られると信じているか、によって決まる、と考えます。
例えば、砂漠で喉がカラカラの旅人にとっては、一杯の水は、一粒のダイヤモンドよりも、遥かに価値があります。このように、物の価値は、個人の置かれた状況や、欲求によって変動する、という考え方を、何と呼ぶでしょう?
- 機会費用
- 主観的価値理論
- インセンティブ設計
解答と解説
その「お宝」の、本当の価値。そのありかを見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『主観的価値理論』(しゅかんてきかちりろん) でした!
これは、近代経済学の、最も基本的な土台となっている、重要な考え方の一つです。
なぜ『主観的価値理論』が、「猫に小判」の謎を解き明かすのか?
「猫」と「小判」が登場する、思考実験をしてみましょう。
- 小判(こばん)
人間にとって、この金貨は、絶大な価値を持ちます。食料や、安全な住処、様々なサービスと、交換することができるからです。その価値は、客観的で、絶対的なものに思えます。 - 猫(ねこ)
さて、猫が、この小判を、じっと見つめています。これは、食べられません。暖かくもないので、上で眠ることもできません。オモチャとしては、最初の数分は楽しいかもしれませんが、ただのボールの方が、よっぽど魅力的です。猫の視点から見れば、この小判の「効用(満足度)」は、ゼロに等しいのです。
『主観的価値理論』は、この状況を、見事に説明します。この理論によれば、「価値」とは、小判という、モノの側に、宿っている性質ではないのです。「価値」とは、それを受け取る側の「心」が、自らのニーズや、好みに基づいて、主観的に決定する、判断なのです。
猫にとっては、一匹の煮干しの方が、一枚の小判よりも、遥かに、主観的な価値が高い。
これは、猫にとっての欲求の優先順位が、人間とは全く異なるからに他なりません。 この「欲求の階層」という考え方を、人間の心理から解き明かしたのが、こちらの「花より団子」の物語です。
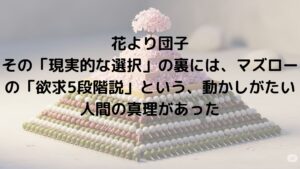
「猫に小判」ということわざは、この、経済学の基本原則を、理解できなかったがゆえの、コミュニケーションの失敗を描写しているのです。 小判を猫に与える人は、「自分にとって価値のあるものは、他者(猫)にとっても、当然、価値があるはずだ」という、自らの価値観を、相手に、一方的に、投影してしまっているのです。贈り物が無駄になったのは、猫が「愚か」だからではありません。贈り手が、相手の、全く異なる「主観的な価値観」を、想像できなかったからなのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 機会費用: これは、ある選択をしたことで「得られなかった」もう一方の選択肢の価値を指す言葉です。価値そのものが、どのように決まるか、という理論ではありません。
- 3. インセンティブ設計: これは、人々が特定の行動を取りたくなるような「動機付け」を設計することです。価値あるものが、インセンティブとして使われることはありますが、その価値の根源を説明する理論ではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 非常に古くから使われている、日本のことわざです。「豚に真珠」と、ほぼ同じ意味で使われます。身近な動物である「猫」と、富の象徴である「小判」という、誰にでも分かる、鮮やかな対比が、その価値のミスマッチを、ユーモラスに伝えています。
- 面白雑学: 17世紀のオランダで起きた、「チューリップ・バブル」という、歴史的な経済事件があります。当時、チューリップの球根という、ただの植物の根っこが、投機の対象となり、その「主観的な価値」が、異常なまでに高騰しました。最盛期には、たった一つの球根が、アムステルダムの豪邸一軒よりも、高値で取引された、と言われています。しかし、その後、バブルは崩壊。球根の価値は、一夜にして、ほぼゼロに戻りました。この事件は、物の価値が、その物自体に内在するのではなく、いかに、人々の、主観的な熱狂や、思い込みによって、形成されるか、という、主観的価値理論の、劇的な実例として、語り継がれています。
まとめ:明日から使える「知恵」
「猫に小判」とは、経済学の基本原則である、「主観的価値理論」の、完璧な寓話です。それは、価値とは、贈り物の側に、客観的に存在するものではなく、それを受け取る側の、主観的なニーズや、欲求、そして、満足度によって、初めて生まれるものである、ということを、私たちに教えてくれます。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『この世に、万物共通の「価値」など、存在しない。相手にとって、本当に価値のある贈り物をしたければ、まず、あなたが「価値がある」と信じているものを、手放し、そして、相手が、何を、心から「価値がある」と感じているのかを、発見することから、始めよ』ということです。
あなたが、誰かに「猫に小判」な贈り物を、してしまった経験はありますか?
この記事では、価値が、いかに「主観的」であるかを、経済学から、解説しました。そして、その、私たちの、主観的な、価値判断は、実は、ある、強力な「認知バイアス」によって、簡単に、操作されてしまう、という、事実を、ご存知ですか? 「雀の涙」ということわざが、その、恐るべき、「アンカリング効果」の、正体を、教えてくれます。
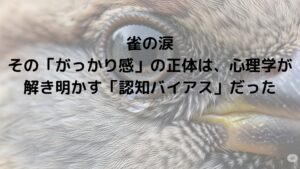
この記事では、「価値のミスマッチ」を経済学の視点から探りました。では、この同じ過ちが、現代の製品開発やサービス設計の世界では、どのように語られているのでしょうか? ほぼ同じ意味を持つ「豚に真珠」ということわざを、「UI/UXデザイン」の観点から解説した、こちらの記事もぜひご覧ください。
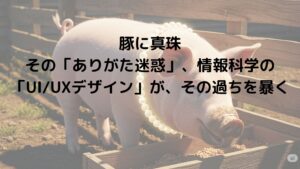
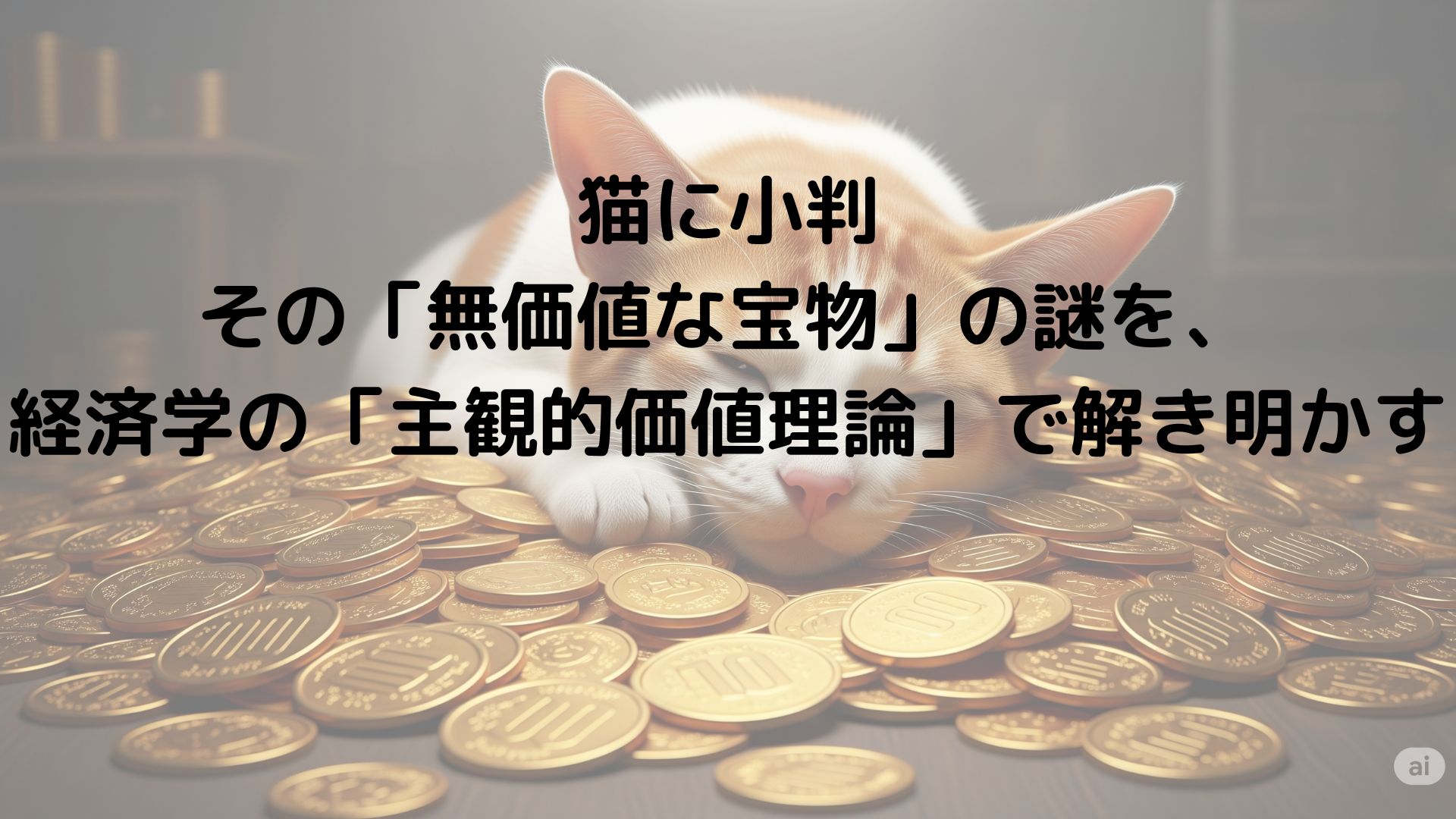

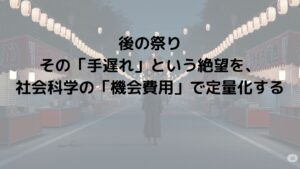
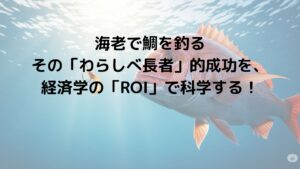
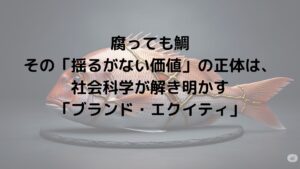
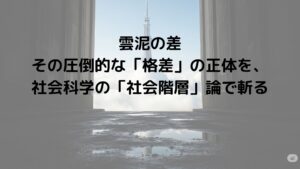
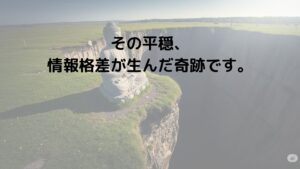
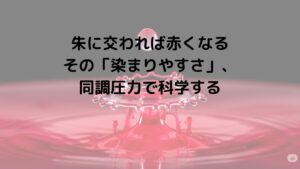
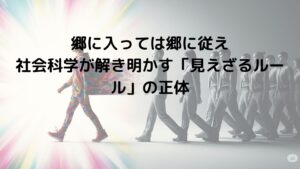
コメント