朝寝坊して、会社に遅刻。慌てて家を飛び出したら、途中で、突然の豪雨に降られ、傘もなくて、ずぶ濡れに…。ああ、まさに泣き面に蜂だ。 あるいは、お財布を落として、交番で手続きをしている、まさにその最中に、ペットが病気になった、という連絡が入る…。どうして、不幸は、こうも重なるのだろうか。
悪いことが起きた時に、まるで狙いすましたかのように、さらに別の、悪い出来事が追い討ちをかける。この、不運の連鎖を、私たちは『泣き面に蜂』と呼びます。
この時、私たちは、つい、「今日は、厄日だ」「何か、悪いものに憑かれているのかもしれない」と、運命や、オカルト的な力を、感じてしまいがちです。
まさに、何度も何度も打ちのめされる、この苦しい状況。 そんな時、折れずに、しなやかに立ち直るための「心の重心」について、物理学の視点から、こちらの記事で解説しています。
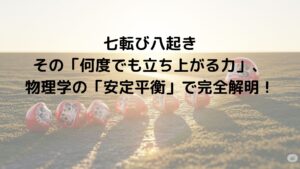
しかし、もし、この「不幸の連鎖」が、単なる「偶然」であり、その正体が、冷徹な数学の法則で、説明できるとしたら…?今回は、このことわざを、自然科学、特に「確率論」という視点から、クイズ形式で、その思い込みを、解き明かしていきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
あなたが、コインを投げて、「裏」が出たとします。あなたは、これを「不運な結果」だと感じました。
さて、あなたは、続けて、もう一度、同じコインを投げます。この時、次に「裏」が出る確率は、どうなっているでしょうか?最初の「不運」な結果は、次の結果に、影響を与えるのでしょうか?
このように、ある事象の発生が、他の事象の発生確率に、全く影響を与えない時、この二つの事象の関係を、確率論では何と呼ぶでしょう?
- 排反事象
- 従属事象
- 独立事象
解答と解説
その「不運の連鎖」を断ち切る、科学的な視点。見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 3. の『独立事象』(どくりつじしょう) でした!
これは、確率論の、最も基本的な、そして、最も重要な考え方の一つです。
なぜ『独立事象』が、「泣き面に蜂」の正体を暴くのか?
「泣き面に蜂」という、一見、不運が連鎖しているように見える状況を、確率論で、分解してみましょう。
- 事象A:「泣き面」になる
例えば、あなたが、ある日に、お財布を落としてしまう、という出来事。これが起きる確率は、非常に低いでしょう。仮に、1万分の1(0.01%)だとします。そして今日、その、非常に不運な、低確率の事象が、起きてしまいました。 - 事象B:「蜂」に刺される
次に、あなたが、ある日に、蜂に刺されてしまう、という出来事。これもまた、非常に確率の低い、不運な事象です。仮に、2万分の1(0.005%)だとしましょう。
ここで、最も重要なのは、確率論の視点に立てば、この二つの事象は、完全に「独立」している、ということです。 あなたが、財布を落としたからといって、蜂が、あなたを狙って飛んでくる、ということは、ありえません。コインは、前回が「裏」だったからといって、次の出目を変えたりはしません。蜂は、あなたが泣いていることなど、知ったことではないのです。
では、なぜ、私たちは、あたかも、そこに「不運の連鎖」という、因果関係があるかのように、感じてしまうのでしょうか? それは、私たちの脳が、本来、無関係な、ランダムな事象の間に、意味や、物語(パターン)を見つけ出そうとする、強力な「クセ」を持っているからです。
財布を落とし(A)、かつ、蜂に刺される(B)、という二つの事象が、同じ日に起きる確率は、1万分の1 × 2万分の1 = 2億分の1。これは、天文学的に低い確率です。 そして、この、天文学的に稀な「偶然の一致」が、いざ、自分の身に起きた時、私たちの脳は、「これは、単なる偶然だ」と、受け入れることができないのです。その代わりに、「今日は、呪われた日だ」「悪いことが、悪いことを呼んでいる」という、**一つの、分かりやすい「物語」**を、作り出してしまうのです。
「泣き面に蜂」とは、「不運が不運を呼ぶ」という、宇宙の法則ではありません。それは、統計学的に、極めて稀ではあるが、起こりうる「独立した不運な事象の、偶然の同時発生」に対する、私たちの、人間的な、心理的反応を、描写した言葉だったのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 排反事象: これは、二つの事象が、決して「同時には起こらない」関係のことです(例:コインを一度投げて、それが「表であり、かつ、裏である」ことはない)。泣きながら、蜂に刺されることは、可能です。
- 2. 従属事象: これは、一方の事象の結果が、もう一方の事象の確率に、「影響を与える」関係のことです(例:トランプの山から、キングを一枚引くと、次にキングを引く確率は、低くなる)。ことわざは、あたかも、こうであるかのように、私たちに感じさせますが、実際には、そうではないのです。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 古くから使われている、日本のことわざです。泣いていて、顔が腫れているところに、さらに、蜂が、その顔を刺す、という、これ以上ないほどの「追い討ち」のイメージが、その悲惨さと、不運の重なりを、非常に分かりやすく、そして、少しユーモラスに伝えています。
- 面白雑学: ギャンブルの世界には、「ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)」という、有名な思考のワナがあります。これは、例えば、ルーレットで、「赤」が5回連続で出た後、「そろそろ、黒が来るはずだ」と、思い込んでしまう心理のことです。しかし、ルーレットの盤は、過去の出目を、一切、記憶していません。次の一回で、赤が出る確率も、黒が出る確率も、常に、ほぼ同じです。これもまた、「泣き面に蜂」と同じ構造の、思考の誤りです。私たちは、ランダムな事象の中に、存在しないはずの、「バランス」や「流れ」を、勝手に見つけ出そうとしてしまうのです。
まとめ:明日から使える「知恵」
「泣き面に蜂」という、不運が重なる感覚。それは、非常にリアルで、辛い体験ですが、多くの場合、それは、あなたの脳が、作り出した「物語(認知の錯覚)」に過ぎません。確率論は、それらの出来事が、それぞれ、無関係な、単なる「独立した偶然」であることを、教えてくれます。
つまり、このことわざが本当に教えてくれる、現代的な教訓とは… 『宇宙は、あなたに、陰謀を企ててはいない。それは、ただ、無関心なだけである。宇宙は、泣いている顔に、蜂を送るのではない。ただ、そこに、蜂を送り出すだけだ。そして、あなたが、たまたま、そこで、泣いているだけなのだ。偶然を、呪いと、取り違えるな』ということです。
あなたが、これまでに経験した、最大の「泣き面に蜂」は何でしたか?今、確率論の視点から、それを、もう一度、見つめ直してみると、何か、新しい発見があるかもしれません。
この記事では、確率論が「不運の連鎖」という幻想を、いかに解き明かすかを見てきました。では、同じ確率論は、私たちが「行動を起こす」ことの、光と影について、何を教えてくれるでしょうか? 「犬も歩けば棒に当たる」ということわざが示す、もう一つの「確率の真理」を、こちらの記事で探求しています。
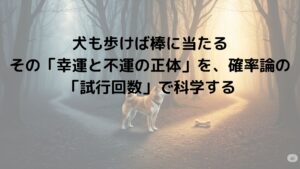
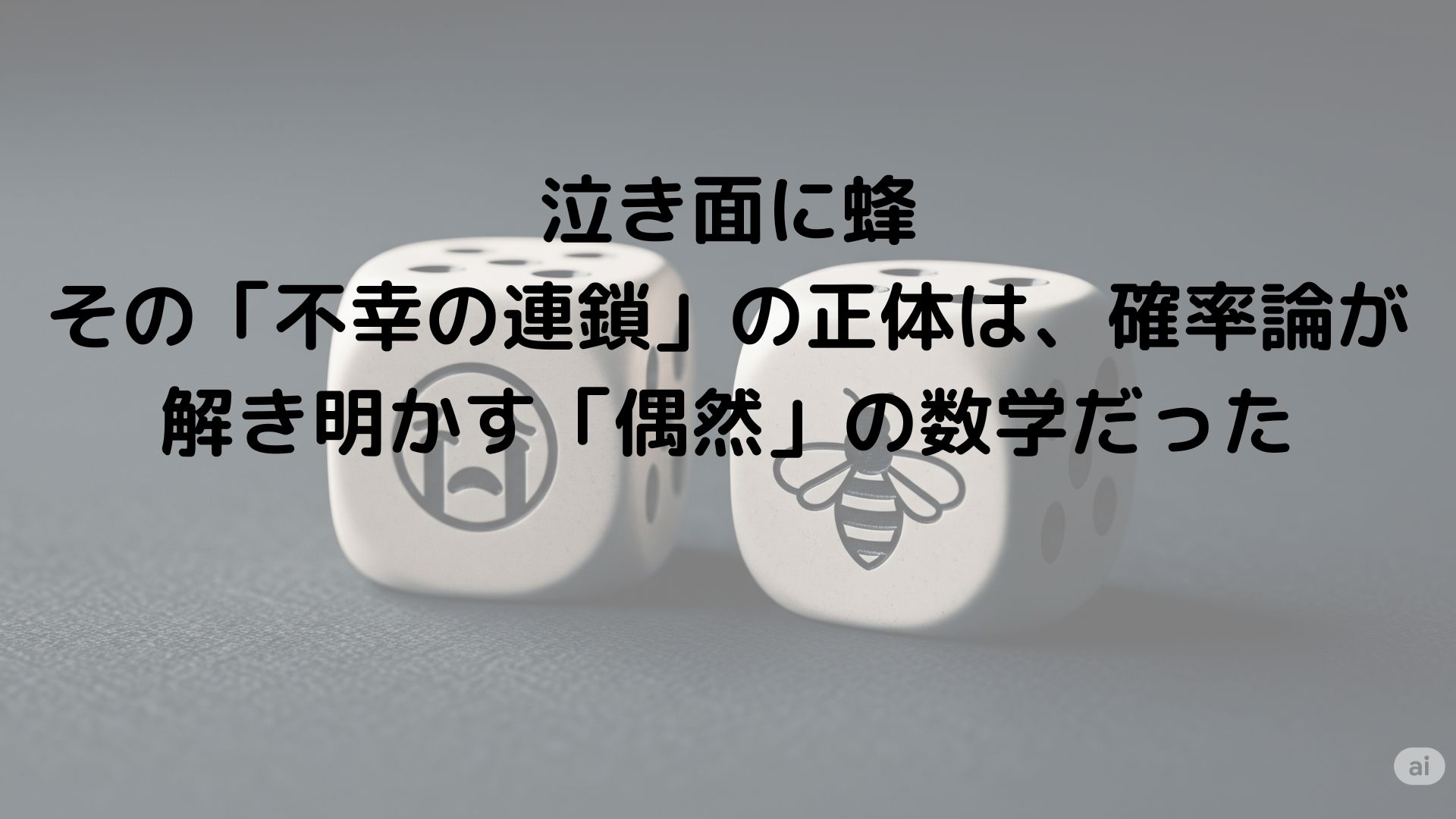
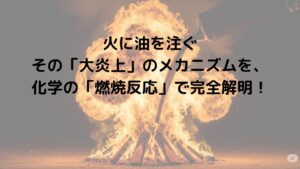
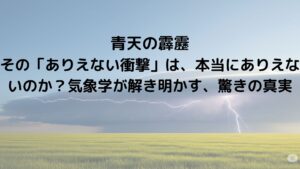
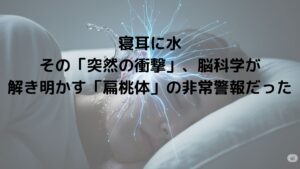
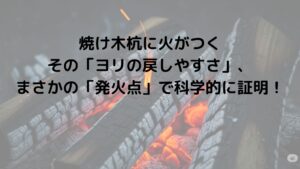
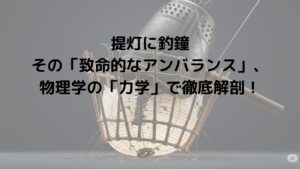
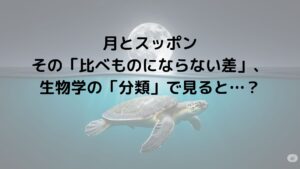
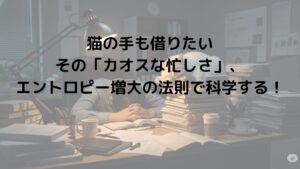
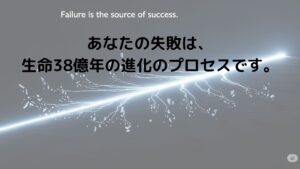
コメント