「お金を節約しようと、自分でパソコンの修理を試みたけど、かえって、事態を悪化させてしまった…。最初から、プロに頼めばよかった。まさに、餅は餅屋だな」 「なぜ、我々マーケティング部が、法律の専門家でもないのに、契約書の草案を作っているんだ?弁護士に相談すべきだ。餅は餅屋だよ」
ある事柄については、素人が、下手に手を出すよりも、その道の専門家に任せるのが、一番良い。この、あまりにも当たり前で、しかし、しばしば、私たちが忘れてしまう、重要な知恵。それが、『餅は餅屋』です。
これは、単なる「当たり前のこと」なのでしょうか?いいえ。実は、このことわざは、私たちの、この、豊かで、複雑な、現代社会全体を、成り立たせている、最も、基本的な「経済原理」そのものなのです。
今回は、このことわざの、その深遠な重要性を、社会科学、特に、近代経済学の父、アダム・スミスの思想を借りて、クイズ形式で、探っていきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
近代経済学の父、アダム・スミスは、その主著『国富論』の中で、社会全体の生産性を、飛躍的に高めるための、ある、基本的な原理を、説きました。
彼は、「ピン(針)」を作る工場を例に挙げ、一人の労働者が、針金の引き抜きから、切断、研磨、頭付けまで、全ての工程を、一人で行うのではなく、それぞれの工程を、別々の労働者が、専門的に、担当することで、社会全体の生産量が、爆発的に増大する、と主張しました。
このように、生産のプロセスを、細分化し、各人が、特定の作業に、特化することを、何と呼ぶでしょう?
- 機会費用
- 分業
- 需要と供給
解答と解説
その「専門家」が、社会に、もたらす、本当の価値。その正体を見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『分業』(ぶんぎょう) でした!
英語では “The Division of Labor” と呼ばれ、私たちの、この、豊かな資本主義社会が、成立するための、大前提となった、極めて重要なコンセプトです。
なぜ『分業』が、「餅は餅屋」の、本当の理由なのか?
昔の、小さな村の、生活を、想像してみてください。
- ケースA:「分業」がない社会
村の、全ての家族が、全てのことを、自分たちで、やろうとします。自分たちで、米を少し作り、魚を少し釣り、狩りを少しして、そして、自分たちで、下手な道具を作っている。 彼らは、あらゆることの「素人」であるため、全ての生産物の質は低く、生産量も少ない。村全体は、貧しく、日々の暮らしで、手一杯です。 - ケースB:「分業」がある社会
ある日、村人たちは、それぞれが、得意なことに「専門特化(分業)」することを、決めました。
・米作りが、誰よりも上手な、田中さん一家は、「米屋」に。
・魚を獲るのが、得意な、鈴木さん一家は、「魚屋」に。
・そして、代々伝わる、秘伝の製法で、最高に美味しいお餅を作れる、佐藤さん一家は、「餅屋」になりました。
さて、どうなったでしょう。
田中さんは、高品質な米を、大量に生産できるようになりました。鈴木さんは、毎日、新鮮な魚を、村にもたらしました。そして、佐藤さんの「餅屋」の餅は、村一番の、名物となりました。
彼らは、自分たちが作ったものを、互いに「交換」することで、以前とは、比べ物にならないほど、豊かで、多様な、食生活を送れるようになったのです。村全体の、幸福度が、飛躍的に、向上しました。
これこそが、『分業』がもたらす、奇跡です。
ことわざ「餅は餅屋」とは、この、社会全体の生産性と、幸福度を、最大化させるための、経済学の、基本原理を、見事に、表現した言葉なのです。
私たちが、餅が食べたくなったら、「餅屋」に行くべきなのは、単に、その方が「美味しいから」だけではありません。それぞれの専門家が、自らの仕事に集中し、その成果を、社会全体で、交換し合うことこそが、社会全体を、最も、豊かにする方法である、という、経済学的な、大原則に基づいた、極めて、合理的な行動なのです。専門家に頼ることは、怠惰ではなく、社会の、発展の、基本なのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 機会費用: これは、何かを選択した時に、諦めた、もう一方の選択肢の価値を指す言葉です。「分業」という、生産の仕組みそのものではありません。
- 3. 需要と供給: これは、ある商品の、需要と、供給の、バランスによって、その価格が決まる、という、市場の原理を指す言葉です。生産の、専門特化を、説明するものではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: このことわざは、日本で、特に、様々な職人や、商人が、その技術を競い合った、江戸時代に、広く、使われるようになりました。それぞれの「道」には、それぞれの「プロ」がいる、という、専門性への、敬意が込められた言葉です。
- 面白雑学: アダム・スミスが、例に挙げた「ピン工場」の話は、非常に、示唆に富んでいます。彼は、一人の、未熟な職人が、全ての工程を、一人で行った場合、一日に、たった、1本のピンすら、作れないかもしれない、と述べました。しかし、たった10人の職人が、それぞれ、一つか、二つの、単純な工程に「分業」することで、その工場は、なんと、一日に、4万8000本ものピンを、生産できるようになった、というのです。これこそ、「分業」がもたらす、生産性の、劇的な向上の、動かぬ証拠です。
まとめ:明日から使える「知恵」
「餅は餅屋」とは、単なる、実用的な、処世術ではありません。それは、近代経済学の、最も、重要な概念の一つである、「分業」の原理を、民衆の知恵として、表現した言葉なのです。専門特化と、その成果の交換こそが、品質、効率性、そして、社会全体の、豊かさを、生み出す、鍵なのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『あなたが、中途半端な餅を、作ることに、人生を、浪費してはならない。自らの技術を磨き、最高の「専門家」になることに、集中せよ。そして、餅のことは、餅の、専門家に、敬意をもって、任せよ。互いの専門性への、信頼こそが、社会を豊かにする、唯一の道である』ということです。
あなたが、最近、「餅屋」に頼らずに、自分でやって、失敗してしまったことは、何ですか?そして、あなた自身が、他の誰にも負けない、と自負する、「専門の餅」は、何でしょうか?
この記事では、「分業」の原理に基づき、社会を発展させるために専門家を信頼することが、いかに合理的で重要であるかを探りました。
しかし、私たちが信頼を寄せる、その道の「専門家」とて、人間です。時には、信じられないようなミスを犯すこともあります。「猿も木から落ちる」ということわざが、なぜ専門家でさえ失敗するのか、その「ヒューマンエラー」のメカニズムを科学的に解き明かし、私たちがその事実にどう向き合うべきかを教えてくれます。
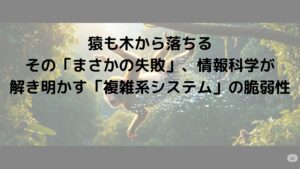

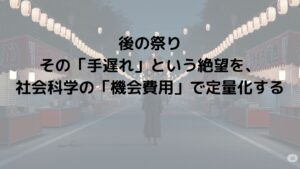
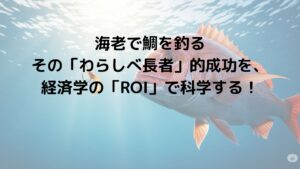
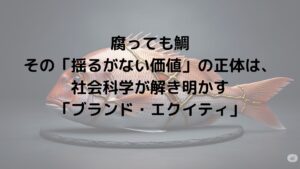
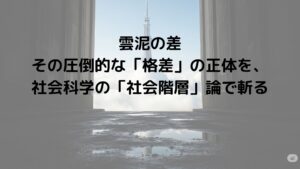
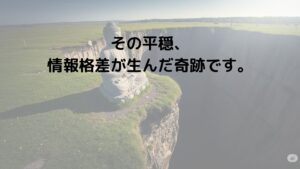
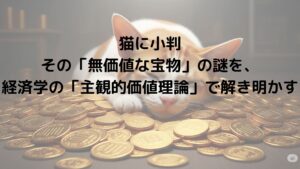
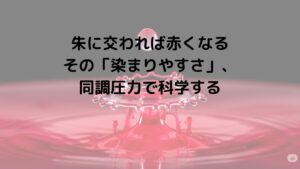
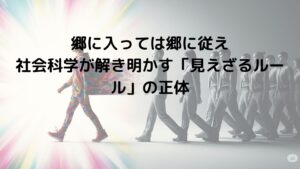
コメント