彼は、神の手を持つとまで言われた、スター外科医。しかし、先日のごく簡単な、日常的な手術で、初歩的なミスを犯してしまったらしい。まさに「弘法にも筆の誤り」だ。 飛行時間3万時間を超える、ベテラン中のベテランパイロットが、着陸の際に、基本的な操作を一つ忘れていた。どんな達人でも、完璧ではいられない。「弘法にも筆の誤り」とは、よく言ったものだ。
その道の第一人者、神様とまで呼ばれるような達人でさえ、時には、信じられないような、初歩的な失敗をすることがあります。この、人間の「完璧ではなさ」を戒める言葉が、『弘法にも筆の誤り』です。
私たちは、これを、単なる「運が悪かった」「たまたま、気の緩みがあった」で片付けてしまいがちです。しかし、実は、この「達人の失敗」の裏には、達人であるがゆえに陥りやすい、特定の「心の罠」が存在するのです。
今回は、このことわざを、心理学の視点から、特に「ヒューマンエラー」の科学として、クイズ形式で分析していきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
自動車の運転や、楽器の演奏、あるいは、タイピングのように、ある技能に習熟し、エキスパートになると、私たちは、いちいち意識しなくても、その行動を、非常にスムーズかつ、効率的に行えるようになります。
しかし、この「意識せずともできてしまう」という状態は、時に、注意が散漫になったり、慣れからくる油断が生まれたりすることで、かえって、ごく簡単な、ありえないようなミスを引き起こす原因ともなり得ます。
このように、熟練の結果、ある行動が、意識的な努力を必要としない、無意識的なプロセスとして、実行されるようになる状態を、心理学では何と呼ぶでしょう?
- 自動化
- 内発的動機づけ
- 認知的不協和
解答と解説
その「達人のうっかり」、そのメカニズムを見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 1. の『自動化』(じどうか) でした!
英語では “Automaticity” と呼ばれ、エキスパートの、驚異的なパフォーマンスの源泉であると同時に、彼らが犯す、特有の「エラー」の原因ともなる、諸刃の剣なのです。
なぜ『自動化』が、「弘法の誤り」を生むのか?
書道の達人、弘法大師(空海)の、筆の動きを想像してみましょう。
- 初心者
文字を書き始めたばかりの初心者は、「まず、横線を引いて、次に、縦線を…」と、一筆一筆、その全てに、意識を集中させなければなりません。脳は、フル回転しています。 - 達人(弘法大師)
しかし、弘法大師にとって、文字を書くという行為は、もはや、呼吸をするのと同じくらい、自然なものです。何十年という鍛錬の末、その動きは、完全に、脳と筋肉にプログラムとして、刻み込まれています。これこそが『自動化』です。この状態にあるからこそ、彼は、筆の運びといった、機械的な作業に脳のリソースを割くことなく、文字の持つ「美」や「精神性」といった、より高次元な領域に、意識を集中させることができるのです。
何十年というこの、長く、時に報われない鍛錬の期間こそが、まさに「石の上にも三年」という状態であり、そのプロセス自体も、実は科学的に解明されています。
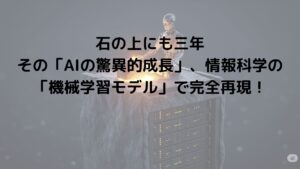
しかし、ここに、巧妙なワナが潜んでいます。 プロセスが「自動化」されている、ということは、それは、「意識的な監視」が、外れている状態でもあるのです。
ある日、弘法大師が、少し疲れていた、あるいは、外の物音に、ほんの一瞬、気を取られたとします。その瞬間、彼の脳内で、完璧に実行されていたはずの「自動筆記プログラム」に、ほんの僅かなグリッチ(不具合)が生じる。そして、普段なら絶対にしないような、線の僅かな誤りが、生まれてしまう。
彼の意識は、より高次元な「美」に向かっているため、この、低レベルな機械的作業のエラーに、気づくのが遅れてしまうのです。
これこそが、熟練者のジレンマです。達人たる所以である「自動化」の能力そのものが、かえって、「無意識的な、初歩的エラー」を生み出す土壌となってしまうのです。達人が失敗するのは、彼が未熟だからではありません。むしろ、彼の技術が、あまりにも自動化され、熟練しすぎているからこそ、失敗するのです。
【不正解の選択肢について】
- 2. 内発的動機づけ: これは、行為そのものから得られる楽しさが、やる気の源になる、というモチベーションの理論です。弘法大師が、書を愛していたのは間違いないでしょうが、それが、彼のエラーの直接的なメカニズムではありません。
- 3. 認知的不協和: これは、心の中に矛盾した考えがある時に感じる不快感のことです。「私は達人のはずなのに、なぜか失敗してしまった」という、エラーの「後」に感じる、心の葛藤はこれにあたりますが、エラーそのものの原因ではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 平安時代の僧侶であり、能書家(書道の達人)として、後世、「三筆」の一人に数えられる、空海(弘法大師)の名を冠したことわざです。「弘法大師ほどの、神のごとき達人でさえ、時には筆を誤ることがある」と、あえて、完璧の象徴とも言える人物を例に出すことで、どんな名人にも間違いはある、という教えを、非常に強く、説得力をもって伝えています。
- 面白雑学: 現代の航空業界では、この「熟練者のエラー」を防ぐための、素晴らしい仕組みがあります。それが「チェックリスト」です。何万時間という飛行経験を持つ、エキスパート中のエキスパートであるパイロットでさえ、離陸前や着陸前には、必ず、声に出して、基本的な操作手順のリストを、一つ一つ確認することが義務付けられています。なぜでしょうか?それは、あまりにも慣れ親しんだ「自動化」された手順の中にこそ、見落としの危険が潜んでいることを、痛いほど知っているからです。チェックリストとは、まさに、「弘法」を、彼ら自身の卓越した専門性から、守るために設計された、偉大なシステムなのです。
まとめ:明日から使える「知恵」
「弘法にも筆の誤り」とは、熟練の極致で起こる、心理学的なパラドックスを、見事に描き出したことわざです。流れるような、達人芸を可能にする、スキルの「自動化」という能力そのものが、時として、意識の監視をすり抜け、初歩的なエラーを生み出す扉を開けてしまうのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『熟練の「自動操縦」を、過信するな。巧みになればなるほど、基本的なことの、確認を怠るな。真の熟達とは、自らの天才性を、疑う謙虚さをも、含んでいるのだ』ということです。
あなたが、自分は「専門家だ」と自負する分野で、思わず「筆の誤り」を犯してしまった、という経験はありますか?
この記事では、達人の脳内で起きる「自動化」という、驚くべきメカニズムを、解説しました。では、この「自動化」が、発動しやすくなる、心理的な「環境」とは、どのようなものでしょうか? 「河童の川流れ」ということわざが、その、「コンフォートゾーン」という、快適で、しかし、危険な、領域の正体を、教えてくれます。
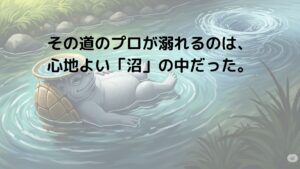
この記事では、「達人の失敗」を心理学の「自動化」という視点から解説しました。しかし、同じ現象を、情報科学の「システムの必然」という、全く異なる視点から解き明かした記事もあります。二つを読むことで、「失敗の本質」がより立体的に見えてくるはずです。
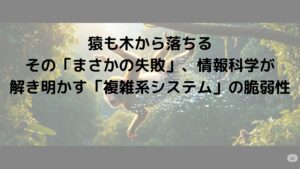
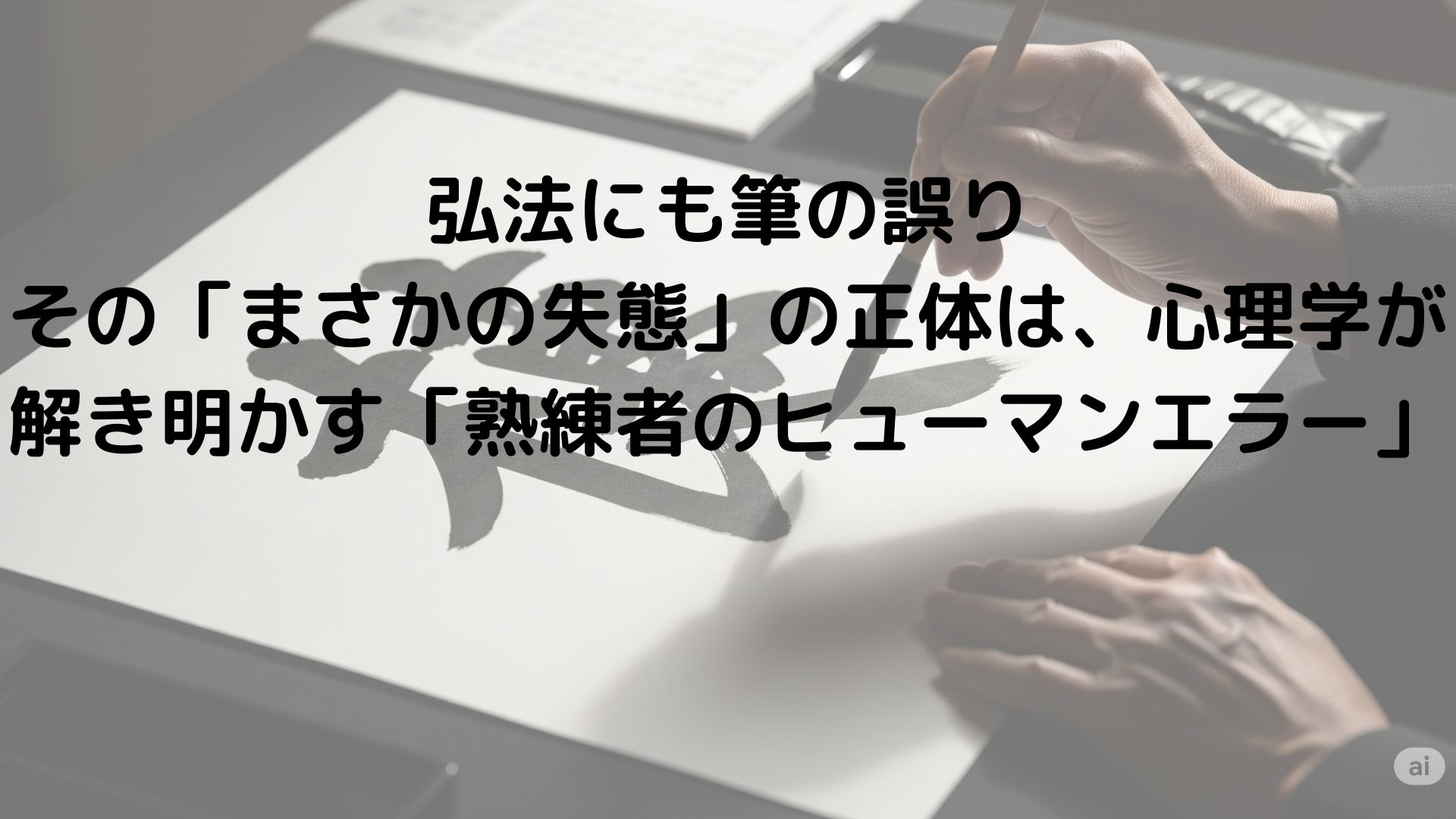
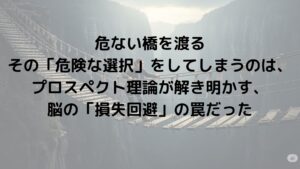
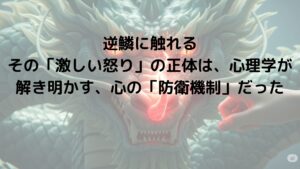
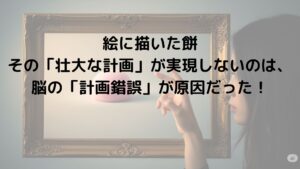
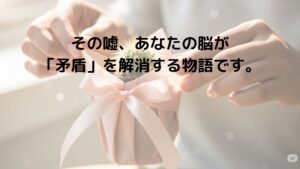
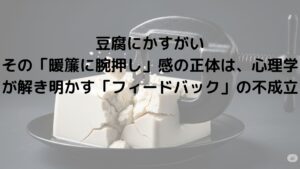
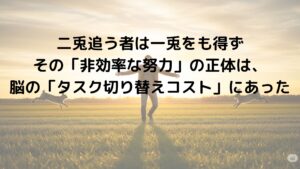
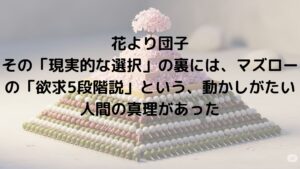
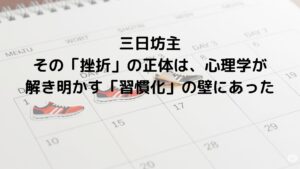
コメント