「このことわざ、どういう意味で覚えてる?」と聞くと、答えが真っ二つに分かれる、不思議な言葉があります。
ある人は、「でしゃばって余計なことをしていると、思わぬ災難にあうよ」という、戒めの意味で。 またある人は、「何でもいいから行動してみれば、思いがけない幸運に出会うかもしれないよ」という、激励の意味で。
それが、『犬も歩けば棒に当たる』です。 果たして、どちらの意味が正しいのでしょうか?実は、その答えは「両方とも正しい」のです。そして、この一見矛盾した二つの意味が両立する理由は、自然科学、特に、「確率論」という数学の分野で、見事に説明することができるのです。今回は、この「運」というものの正体を、科学の視点から紐解いていきましょう。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
確率論の世界では、何かを「試す」行為を「試行」と呼びます。例えば、コインを1回投げるのは「1回の試行」です。
試行の回数を増やせば、それだけ、様々な結果が起こる機会が増えます。例えば、コインを100回投げれば、表も裏も、それぞれ何十回と出ることでしょう。「大成功」と「大失敗」が、どちらも非常に低い確率で起こる、という試行があったとします。この試行の回数を、非常に多く増やした場合、結果はどうなると考えられるでしょうか?
- 常に良い結果が出る確率が高まる
- 良い結果と悪い結果の両方が、起こる絶対数が増える
- 常に悪い結果が出る確率が高まる
解答と解説
あなたの「運命」を左右する、確率の法則。見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の「良い結果と悪い結果の両方が、起こる絶対数が増える」 でした!
これが、このことわざが持つ、二つの意味の核心に迫る、科学的な答えです。
なぜ『確率論』が、「犬も歩けば棒に当たる」の二面性を解き明かすのか?
「犬」を、人生という名の広大なフィールドを探検する、冒険者だと考えてみましょう。
- ケースA:歩かない犬
犬が、自分の犬小屋から一歩も出なかったとします。彼が、何かに出会う「試行回数」はゼロです。彼は、木の棒で殴られる(=不運)こともありませんが、美味しそうな骨付き肉(=幸運)を見つけることもありません。彼の人生は、安全ですが、何の変化もない、中立なものです。 - ケースB:歩き回る犬
さて、犬が、意を決して、広大なフィールドを「歩き回り」始めました。これは、彼が、人生における「試行回数」を、自らの意思で増やしている、ということを意味します。彼は、様々な「偶然の出来事」との遭遇確率を、高めているのです。
確率論は、この先に何が起こるかを、冷徹に教えてくれます。試行回数を増やすことで、犬は、あらゆる可能性のある出来事に遭遇する絶対数を、その確率に応じて、増やしていくことになるのです。
- 棒に当たる(不運):フィールドで、誰かに、いきなり棒で殴られる確率は、非常に低いでしょう。しかし、ゼロではありません。犬が歩き回る時間が長ければ長いほど、いつか、その「低確率の不運」に遭遇する可能性は、確実に高まっていきます。
- 棒に当たる(幸運):フィールドに、誰かが落とした、便利な「棒(=幸運のアイテム)」が落ちている確率も、同様に低いでしょう。しかし、これもゼロではありません。犬が歩き回れば、いつか、その「低確率の幸運」を拾う可能性もまた、高まっていくのです。
つまり、「犬も歩けば棒に当たる」ということわざが持つ、二つの矛盾した意味は、矛盾ではなかったのです。それらは、「行動(試行回数を増やす)」という行為がもたらす、確率論的な、二つの側面に過ぎません。
- ネガティブな意味(戒め):行動すれば、それだけ、リスクに遭遇する確率も上がるのだぞ。
- ポジティブな意味(激励):行動すれば、それだけ、チャンスに遭遇する確率も上がるのだぞ。
科学は、「歩くべきか、歩かざるべきか」という価値判断はしません。しかし、その選択が、どのような結果を確率的にもたらすかを、明確に示してくれるのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. と 3.:試行回数を増やしても、一回あたりの「当たり」や「ハズレ」の確率そのものが変わるわけではありません。あくまで、様々な結果が「起こる機会」が増える、ということです。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 日本の「いろはかるた」の、冒頭の「い」の札として、最も有名なことわざの一つです。元々の意味は、ほぼ間違いなく、「でしゃばると、ろくな事がない」という、ネガティブな戒めの意味でした。それが、時代と共に、行動を奨励する、ポジティブな意味でも使われるようになってきた、と考えられています。社会の価値観の変化が、ことわざの意味すらも変容させた、面白い例です。
- 面白雑学: 「起業」という行為もまた、「犬も歩けば棒に当たる」の、究極の実践例と言えるでしょう。ほとんどのスタートアップは、失敗します(=棒に当たる)。しかし、成功した起業家たちは、皆、この高い失敗確率を受け入れた上で、行動を起こしています。なぜなら、彼らは、行動しなければ(=犬が歩かなければ)、成功確率が、完全にゼロであることを知っているからです。彼らは、自ら「試行回数」を増やすことで、天文学的に低い「大当たりの棒」を探し当てようとする、確率の達人なのです。
まとめ:明日から使える「知恵」
「犬も歩けば棒に当たる」という、二つの顔を持つことわざ。その正体は、「行動は、良くも悪くも、偶然の遭遇確率を高める」という、確率論の基本原理でした。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『何もしなければ、安全だが、報酬もゼロ。行動すれば、リスクとチャンスの両方に、身を晒すことになる。運とは、良くも悪くも、試行回数のゲームであり、そのゲームは、あなたが、一歩を踏み出した時にこそ、始まるのだ』ということです。
あなたの人生において、あなたは、災難の「棒」を恐れますか?それとも、幸運の「棒」を、探し求めますか?
この記事では、「行動」が、良い結果と悪い結果の両方の可能性を、いかに高めるかを解説しました。では、もし「悪い結果」ばかりが、連続して起きたら、どう考えればいいのでしょうか? 「泣き面に蜂」ということわざが教えてくれる、不運の連鎖の、意外な正体とは。
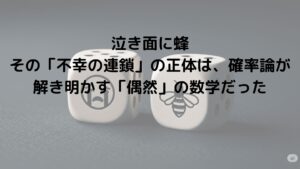
この記事では、運のゲームに参加するために「歩き出す」ことの重要性をお伝えしました。しかし、その「最初の一歩」を踏み出し、継続すること自体が、最も難しいと感じていませんか? 実は、その「続かない」問題にも、科学的な解決策が存在します。
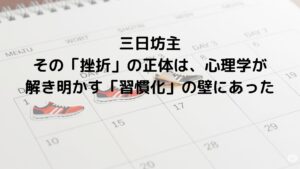
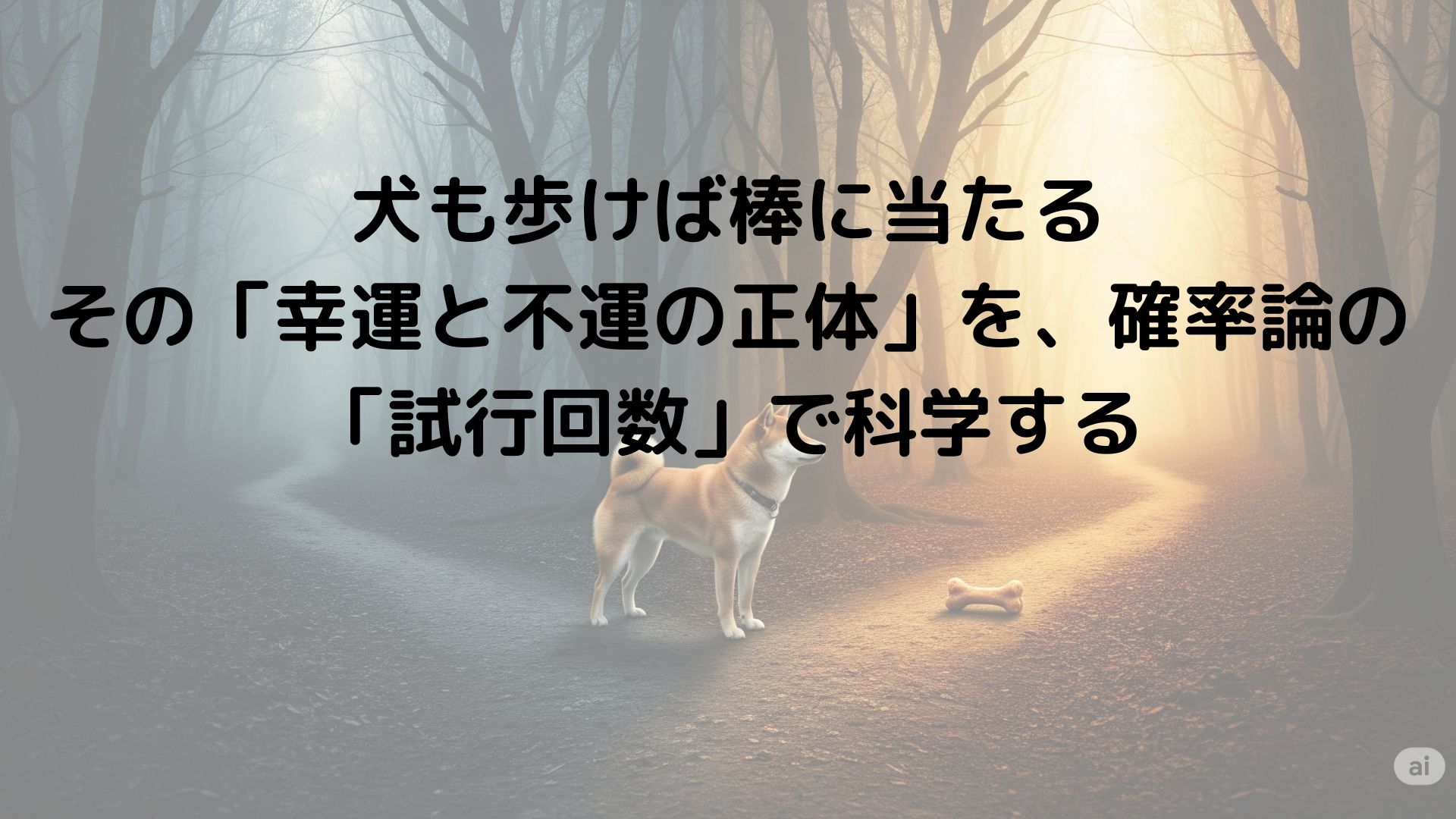
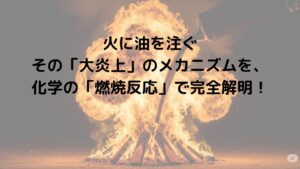
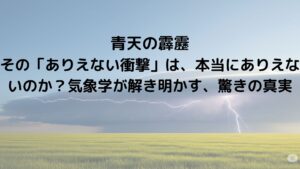
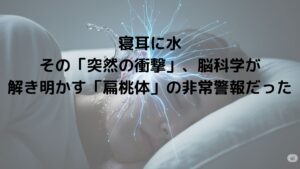
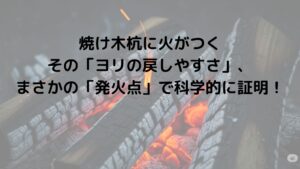
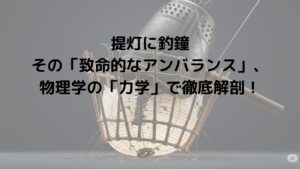
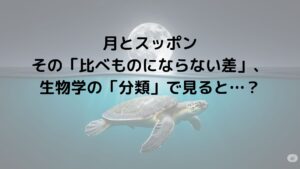
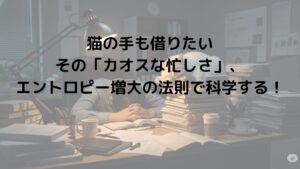
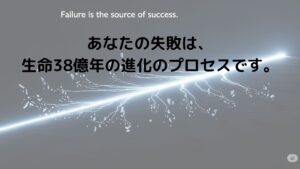
コメント