「うちの新人、何度、仕事のやり方を指導しても、全く響いている様子がない。まさに豆腐にかすがいだよ…」 「やる気のない相手に、どんなに熱く、その仕事のやりがいを説いても、暖簾に腕押し。豆腐にかすがいとは、このことだな」
どんなに、効果的なはずの働きかけをしても、相手の反応が全くなく、何の手応えもないこと。この、虚しさに満ちた状況を、私たちは『豆腐にかすがい』と表現します。
このことわざ、「糠(ぬか)に釘」と、ほとんど同じ意味で使われますよね。しかし、そこには、微妙な、しかし、重要なニュアンスの違いが隠されています。「糠」が、こちらの働きかけを、ただ、するりと受け流してしまうのに対し、「豆腐」は、あまりに柔らかく、脆いために、働きかけによって、形そのものが崩れてしまう可能性さえ、含んでいるのです。
今回は、この「手応えのなさ」の正体を、心理学の視点から、「フィードバック」という概念を軸に、クイズ形式で探っていきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
他者からのアドバイスや、指導、あるいは、批判といった「働きかけ」が、相手の行動を、効果的に変化させるためには、まず、相手が、その「働きかけ」を、正しく受け止め、理解し、そして、それに基づいて、自らの行動を修正しよう、という意志を持つ必要があります。
もし、相手が、無気力であったり、あるいは、精神的に非常に脆く、少しの指摘でも、心が「崩れて」しまったりする状態であれば、どんなに的確な「働きかけ」も、意味をなしません。
このように、ある人の行動の結果(アウトプット)が、次の、その人の行動(インプット)に影響を与える、という、この、一連の、情報の循環プロセスのことを、学習理論や、コミュニケーション論では、何と呼ぶでしょう?
- フィードバック・ループ
- コンフォートゾーン
- 認知バイアス
解答と解説
その「手応えのない」相手との、不毛なやり取り。その構造を見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 1. の『フィードバック・ループ』 でした!
これは、人が学習し、成長していく上で、欠かすことのできない、コミュニケーションの、基本的なサイクルです。
なぜ『フィードバック・ループ』の不成立が、「豆腐にかすがい」の正体なのか?
誰かに、アドバイスをする、という行為を、この「フィードバック・ループ」で、考えてみましょう。
- かすがい(=フィードバック)
「かすがい(鎹)」とは、木材と木材を、繋ぎ止めるための、コの字型の、大きな釘です。あなたの、的確なアドバイスや、厳しい指摘は、まさに、この「かすがい」。相手の問題点を修正し、より良い状態へと、繋ぎ止めるための、強力な「ツール」です。これは、あなたからの「アウトプット」です。 - 豆腐(=フィードバックの受け手)
そして、そのアドバイスを受ける相手が、「豆腐」です。ご存知の通り、豆腐は、極めて、柔らかく、そして、脆い。 - ループの不成立
さて、あなたは、その強力なツール「かすがい」を、「豆腐」に、打ち込もうとします。どうなるでしょう?
豆腐は、柔らかすぎて、かすがいを、全く、受け止めることができません。それどころか、かすがいを打ち込む、という、その衝撃だけで、豆腐は、ぐしゃりと、その形を崩してしまいます。
あなたの「かすがい」は、何の機能も果たさず、ただ、虚しく、豆腐を通過するか、あるいは、豆腐そのものを、破壊してしまう。ここに、フィードバック・ループの、完全な断絶が、生まれるのです。
ことわざ「豆腐にかすがい」とは、この「フィードバック・ループの、受信側における、致命的なエラー」を、見事に描写した、心理学的なメタファーなのです。
「糠に釘」が、相手の「無抵抗・無反応」を、強調するのに対し、「豆腐にかすがい」は、相手が、「抵抗できないほどに、脆い」という、ニュアンスを含んでいます。だからこそ、こちらの働きかけが、無意味であるだけでなく、時として、相手を、精神的に「崩して」しまう、という危険性すら、示唆しているのです。
心理学的に言えば、これは、「相手の、心の状態(=豆腐)に合わせて、適切なツール(=フィードバックの方法)を選べ」という、教えでもあります。豆腐には、かすがいと金槌ではなく、もっと、そっと、優しく触れるような、アプローチが必要だ、ということですね。
【不正解の選択肢について】
- 2. コンフォートゾーン: これは、人が、不安を感じないでいられる、心理的な安全地帯のことです。フィードバックが、このゾーンを脅かすことはありますが、ループそのものを指す言葉ではありません。
- 3. 認知バイアス: これは、物事を判断する際の、思考のクセや偏りのことです。フィードバックを、正しく受け取れない原因が、このバイアスにある場合はありますが、これもまた、プロセスそのものではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 古くからある、日本のことわざです。「かすがい」は、伝統的な木造建築で、木材同士を繋ぎ止めるために使われる、非常に重要な、鉄製の釘です。その、堅牢な「かすがい」と、最も柔らかく、脆い食べ物の一つである「豆腐」との、ありえない組み合わせが、その行為の、無意味さを、滑稽なほどに、強調しています。
- 面白雑学: ビジネスの世界で、部下へのフィードバックの手法として、「サンドイッチ・メソッド」というものがあります。これは、厳しい指摘(=お肉)を、ポジティブな褒め言葉(=パン)で、挟み込む、という手法です。「(パン)君の、この前のプレゼン、すごく良かったよ。→(肉)ただ、ここのデータ分析が、少し、甘いかな。→(パン)でも、全体としては、素晴らしい出来だった。期待しているよ」。これは、相手が「豆腐」のように、精神的に脆い場合に、批判という「かすがい」を、直接、打ち込むのではなく、クッションを置くことで、相手が「崩れる」のを防ぎ、フィードバック・ループを、正常に機能させよう、という、心理学的な工夫なのです。
この、衝撃に弱く、崩れやすい「豆腐」の状態は、まさに、何度倒されても、自ら起き上がる「だるま」の、真逆の構造と言えるでしょう。 その、驚くべき「自己修復能力」の秘密を、物理学の視点から、こちらの記事で解説しています。
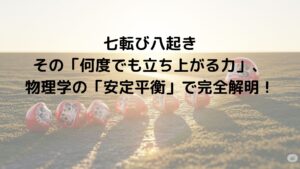
まとめ:明日から使える「知恵」
「豆腐にかすがい」とは、単に「無駄な努力」を指す、ことわざではありません。心理学的に見れば、それは、フィードバック・ループの断絶、すなわち、あなたの働きかけが、相手の、精神的な「脆さ」や、「受け入れ態勢の不備」によって、完全に、無力化されてしまう、という、コミュニケーションの失敗を描写しているのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『あなたの、その的確なアドバイス(かすがい)の有効性は、その鋭さ以上に、あなたが、それを、打ち込もうとしている相手の「材質」によって、決まる。大工の道具を、詩人の心に、使ってはならない』ということです。
あなたが、誰かにとっての「豆腐」だった、と感じた経験はありますか?
この記事では、「相手の脆さ」に起因する、心理学的な手応えのなさを解説しました。では、よく似たことわざである「糠に釘」が示す、「相手の無抵抗さ」に起因する、物理学的な手応えのなさとは、一体、何が違うのでしょうか? その、科学的な違いを、こちらの記事で、ぜひ、見比べてみてください。
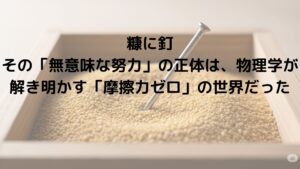
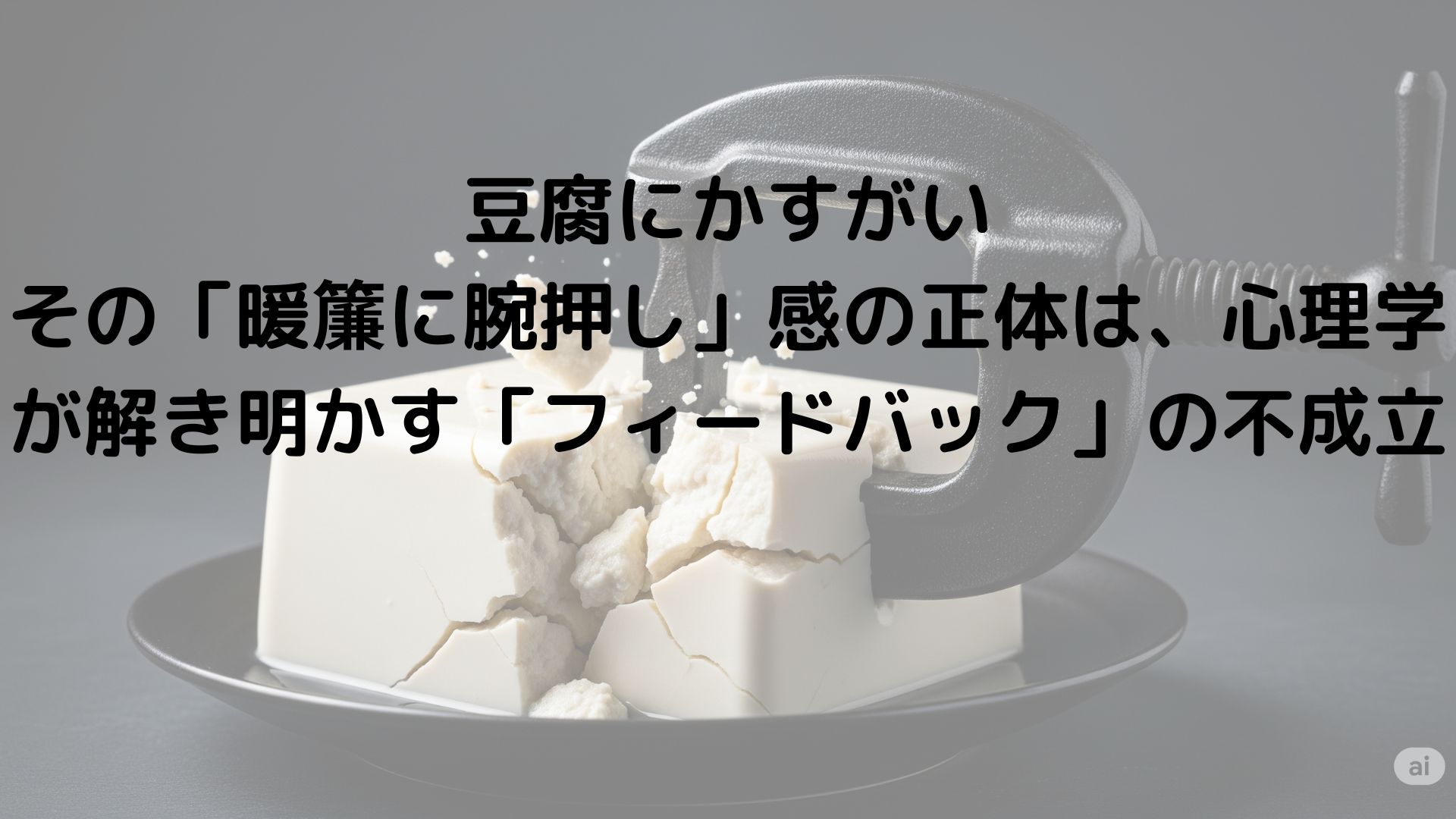
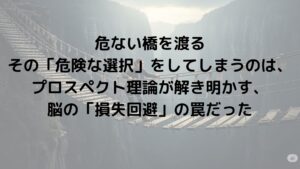
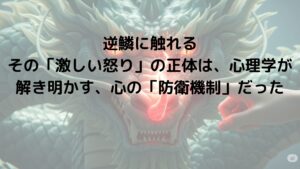
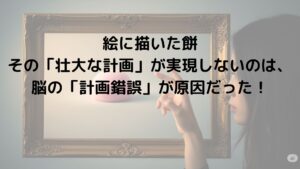
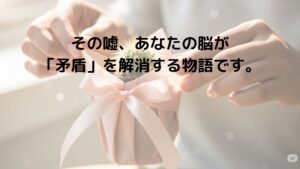
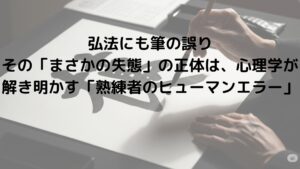
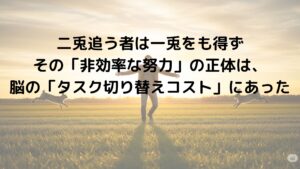
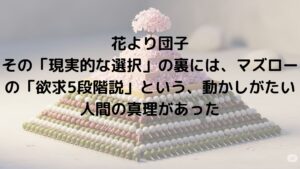
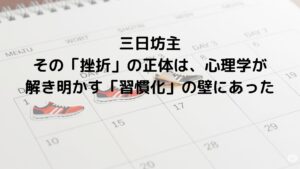
コメント