「うちのおばあちゃん、パソコンなんて全く興味ないのに、叔父さんが、誕生日に、最新スペックの超高級PCをプレゼントしたんだ。もちろん、一度も使われずに、埃をかぶってるよ。まさに豚に真珠だね」 「うちの開発チームが、100個ものすごい機能を詰め込んだ、超複雑なアプリを作ったんだ。でも、顧客が本当に欲しかったのは、たった一つの機能が、ただ、完璧に動くことだけだった。典型的な豚に真珠さ」
価値のあるものを、その価値が分からない相手に与えてしまい、せっかくの行為が無駄になってしまうこと。この、なんとも滑稽で、少し物悲しい状況を、私たちは『豚に真珠』と呼びます。
この時、私たちは、つい「価値が分からない、豚が悪い」と考えてしまいがちです。しかし、本当にそうでしょうか?もしかしたら、悪いのは、「相手を理解せずに、一方的に真珠を渡した」側にあるのかもしれません。
今回は、このことわざを、情報科学、特に、現代のあらゆる製品やサービス設計の根幹をなす、「UI/UXデザイン」の視点から、クイズ形式で、その本質を問い直していきます。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
製品や、アプリ、サービスなどを設計する際、作り手の自己満足ではなく、それを使う「ユーザー」が、何を必要とし、どんな能力を持ち、どのような状況で使うのか、を深く理解することが、極めて重要です。
そして、そのユーザーにとって、ただ高機能なだけでなく、直感的で、使いやすく、そして、心から「使ってよかった」と思えるような、ポジティブな「体験」を提供することを目指します。
このように、徹底的に、ユーザーの視点や満足度を、最優先する設計思想のことを、情報科学の分野では、一般的に何と呼ぶでしょう?
- データベース
- アルゴリズム
- UI/UXデザイン
解答と解説
あなたの「親切」や「仕事」、相手に、本当に価値が伝わっていますか? それでは、正解の発表です!
正解は… 3. の『UI/UXデザイン』 でした!
UIは「ユーザーインターフェース(接点)」、UXは「ユーザーエクスペリエンス(体験)」の略。この二つは、現代のものづくりにおいて、最も重要な概念です。
なぜ『UI/UXデザイン』が、「豚に真珠」の過ちを暴くのか?
あなたが、世界一の、天才料理人だと想像してみてください。 あなたは、希少な食材と、最先端の調理技術を駆使して、誰もが息をのむほど、美しく、複雑で、芸術的な、フルコースの料理を完成させました。これぞ、あなたの「真珠」です。
さて、あなたの目の前にいる、お客様は、誰でしょう。それは「豚」です。…もちろん、これは比喩です。このお客様は、非常にシンプルで、分かりやすいものを求めているユーザー、例えば、「お腹を空かせた、元気な子ども」だと考えてみてください。
あなたはその子に、自信満々で、その芸術的なフルコースを提供します。しかし、子どもは、困惑しています。見たこともない食材、複雑すぎる味付け。彼が本当に欲しかったのは、ほかほかの、塩が効いた、シンプルな「おにぎり」だったのです。あなたの、あの素晴らしい「真珠」は、完全に、無駄になってしまいました。
これこそが、UI/UXデザインの、典型的な失敗例です。
- UI(ユーザーインターフェース)の失敗:あなたの料理という「製品」の、インターフェース(見た目、構成)が、ユーザー(子ども)にとって、あまりに複雑すぎた。
- UX(ユーザーエクスペリエンス)の失敗:ユーザー(子ども)が、その製品を使った「体験」は、喜びではなく、むしろ、混乱と、不満だった。
優れたUI/UXデザイナーは、「自分が、価値があると思うもの」を、ただ作る人ではありません。彼らは、まず、徹底的に、ユーザーを研究します。「この豚(ユーザー)は、本当は何を求めているんだ?」と。そして、もし、相手がおにぎりを求めていると分かれば、彼らは、芸術的なフルコースではなく、その子が、人生で食べた中で、一番美味しい!と、涙を流すほどの、究極の「おにぎり」を作ることに、全力を注ぐのです。
ことわざ「豚に真珠」とは、全ての「作り手」や「伝え手」に対する、時代を超えた、強烈な警告なのです。物の価値は、それ自体に宿るのではありません。それは、受け取る側の、ニーズや、文脈、そして、体験によってはじめて、生まれるものなのです。相手が価値を理解できないものを与えるのは、親切ではなく、単なる「設計の失敗」に過ぎないのかもしれません。
【不正解の選択肢について】
- 1. データベース: これは、データを保存しておくための、システムの裏側の仕組みです。ユーザーが直接触れる、表側の設計思想ではありません。
- 2. アルゴリズム: これは、問題を解決するための、計算手順です。UI/UXは、その結果を、いかにユーザーに分かりやすく、快適に届けるか、という、より広い設計思想を指します。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: この言葉の起源は、新約聖書の「マタイによる福音書」にある、イエスの言葉、「聖なるものを犬に与えるな。また、あなたがたの真珠を豚の前に投げるな。彼らがそれらを足で踏みつけ、向き直って、あなたがたにかみついてくるだろう」に由来します。「豚に真珠」は、この警告の前半部分を、的確に抜き出したものです。
- 面白雑学: ソフトウェア開発の世界には、「機能クリープ」あるいは「ブロートウェア(肥大化したソフト)」という問題があります。これは、開発者が、良かれと思って、次から次へと、新しい、複雑な機能(=真珠)を、製品に追加していった結果、大多数のユーザーが、全く必要としていない機能だらけになってしまう、という現象です。その結果、ソフトは、動作が遅くなり、使い方が分かりにくくなり、ユーザーの満足度は、かえって低下してしまいます。これは、まさに、企業が、ユーザーを無視して、大量の「真珠」を、投げつけ続けている、「豚に真珠」の、典型的な現代の例と言えるでしょう。
そして、この「ユーザーを無視する作り手」とは、まさに、自らの知識や経験という「井戸」の中に閉じこもった、「井の中の蛙」そのものなのです。
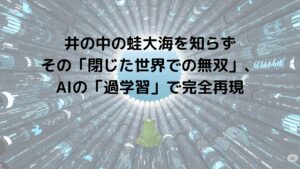
まとめ:明日から使える「知恵」
「豚に真珠」とは、単に「無駄な贈り物」を指す言葉ではありません。情報科学と、デザインの世界の言葉で言えば、それは、UI/UXデザインの、致命的な失敗なのです。それは、相手のニーズ、文脈、そして、あなたが提供する価値を、正しく受け取る能力を、理解し損ねた、という、コミュニケーションの失敗なのです。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『価値とは、作り手が決めるものではない。使い手が、決めるものである。あなたの、その大切な“真珠”を差し出す前に、まず、目の前の相手を、深く、理解する時間を持て。最高の贈り物とは、あなたが価値があると思うものではなく、相手が、役に立つと感じるものなのだ』ということです。
あなたが、誰かから「ありがた迷惑」な「真珠」を、もらった経験はありますか?
この記事では、ユーザーの「ニーズ」を理解することの、重要性を解説しました。では、そのニーズに応える製品を、どうすれば「説明書いらず」で、直感的に、使いやすく、設計できるのでしょうか? 「百聞は一見に如かず」ということわざが、その、もう一つの、重要なデザイン思想を、教えてくれます。
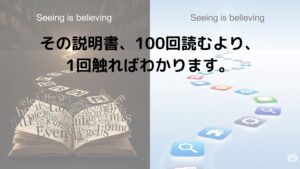
製品開発における「価値のミスマッチ」は、時に、大きな損失を生みます。では、もし、このミスマッチが、国家間の「外交」の舞台で起きたとしたら…? 「馬の耳に念仏」という、さらに壮大なスケールで、同じ原理を解説したのが、こちらの記事です。
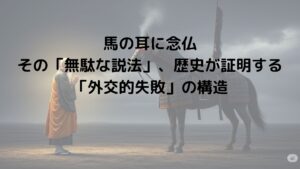
この記事では、「作り手」の視点から「価値のすれ違い」を探りました。この問題の根底にある、近代経済学の基本原則「主観的価値理論」について、「猫に小判」ということわざを通して、より深く学んでみませんか?
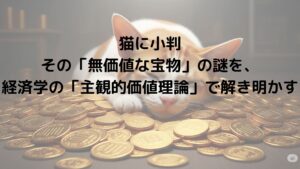
この記事では、「相手のニーズを理解する」ことの重要性を説きました。では、そのニーズには、どのような「優先順位」があるのでしょうか? 人間の根源的な欲求を、心理学の視点から解き明かした、こちらの「花より団子」の記事も、ぜひご覧ください。
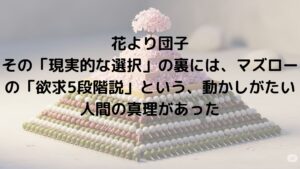
「豚に真珠」という、悲しいすれ違いを前にした時、私たちは、波風を立てないために、つい、心にもない「お世辞」を言ってしまうことがあります。その、「優しい嘘」をついた時、私たちの心の中で、一体、何が起きているのでしょうか? 「嘘も方便」ということわざが、その、巧妙な、自己正当化のメカニズムを、教えてくれます。
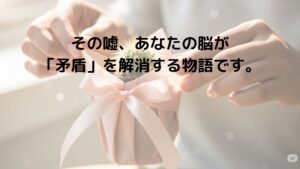

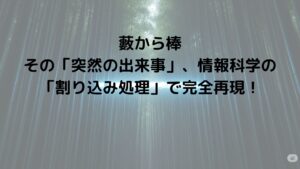
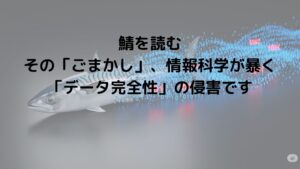
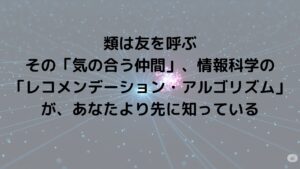
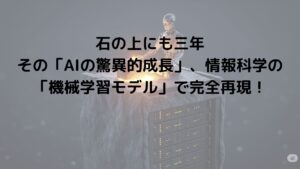
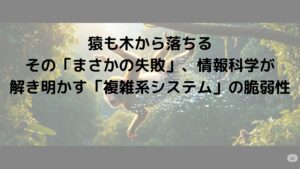
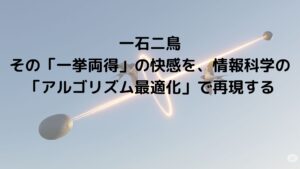
コメント