受験に二度失敗したが、諦めずに三度目の挑戦で、見事、第一志望に合格した。彼の、あの七転び八起きの精神には、本当に頭が下がる。 彼女は、三つの事業を立ち上げては失敗したが、四度目に始めたビジネスが大成功を収め、今では業界の寵児だ。まさに七転び八起きを体現したような人だ。
何度失敗しても、何度打ちのめされても、屈することなく、再び立ち上がる。この、不屈の精神を表す、日本で最も愛される言葉の一つが『七転び八起き』です。
しかし、そもそも、なぜ、私たちは、その「失敗」を、恐れる必要がないのでしょうか? もし、「失敗」が、単なる、乗り越えるべき障害ではなく、より大きな「成功」のための、必要不可欠な「土台」なのだとしたら…?
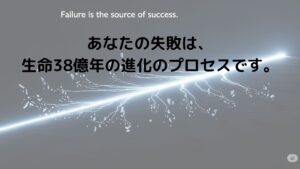
今回は、この、驚くべき「復元力」は、単なる根性や、強い意志だけの問題なのでしょうか?
この、驚くべき「復元力」は、単なる根性や、強い意志だけの問題なのでしょうか?もし、この精神が、ある単純な「設計」によって、物理学の法則に、完璧に裏付けられているとしたら…?
今回は、このことわざを、その精神を最もよく体現する、あの愛すべき「だるま」と共に、科学の視点から、クイズ形式で探求していきましょう。
挑戦状!ことわざ深掘りクイズ
「だるま」や「起き上がり小法師」は、指で突いて、どんなに傾けても、必ず、元のまっすぐな姿勢に戻ってきます。
この驚くべき安定性は、その構造に秘密があります。つまり、人形の、丸い底の部分に、意図的に「おもり」を入れることで、全体のバランスを、極端に下に偏らせているのです。このように、物体の、重さの中心とみなせる一点のことであり、その位置が、物体の安定性を決定づける、物理学における、この点のことを何と呼ぶでしょう?
- 慣性
- 重心
- 作用点
解答と解説
その「折れない心」の、物理的な秘密。見抜くことができましたか? それでは、正解の発表です!
正解は… 2. の『重心』(じゅうしん) でした!
英語では “Center of Gravity” と呼ばれ、物体の安定性を考える上で、最も基本となる、重要な概念です。
なぜ『重心』が、「七転び八起き」の秘密なのか?
「七転び八起き」の完璧なシンボル、「だるま」の、シンプルで、しかし、天才的な物理設計を見てみましょう。
だるまの秘密は、その極端に低い「重心」にあります。底に入れられた重りのおかげで、だるま全体の重さの中心は、限りなく、その底面に近づいています。物理学の世界では、物体は、その「重心」が、最も低い位置にある時に、最も安定した状態、すなわち「安定平衡」にある、とされています。
さて、あなたが、指で、だるまを横に倒した(=転ばせた)とします。この時、あなたは、だるまの重心を、その最も安定した低い位置から、強制的に、高い位置へと持ち上げているのです。
そして、あなたが指を離した瞬間、物理法則が作動します。あらゆる物体は、常に、よりエネルギーの低い、安定した状態へと移行しようとします。だるまにとって、それは、持ち上げられた重心が、重力に従って、再び、最も低い、元の位置へと戻ろうとすることを意味します。
この、重心が元に戻ろうとする力が、だるまの本体を回転させ、自動的に、まっすぐな姿勢へと復元させるのです。だるまが「起きる」のは、魔法でも、意志の力でもありません。それは、この宇宙を支配する、重力の法則に従った、必然的な結果なのです。
ことわざ「七転び八起き」は、私たちに、「だるまのように生きよ」と教えてくれます。人生で、真のレジリエンス(復元力)を持つためには、私たちもまた、低く、安定した「重心」を持つ必要があるのです。
では、人間にとっての「重心」とは何でしょう?それは、決して揺らぐことのない、中核的な価値観かもしれません。あるいは、どんな時も自分を支えてくれる、家族や友人との絆かもしれません。あるいは、人生の目的そのもの、深い自己肯定感かもしれません。
人生の困難(=外からの力)が、私たちを打ちのめし、転ばせようとする時。この、重く、安定した「心の重心」こそが、重力の法則のように、必ず、私たちを、再び、まっすぐに立ち上がらせてくれる力となるのです。
【不正解の選択肢について】
- 1. 慣性: これは、物体が、その運動の状態を維持し続けようとする性質のことです。傾いた物体が、なぜ元の位置に戻るのか、を説明するものではありません。
- 3. 作用点: これは、物体に力が加えられる、その「点」のことです。重心のように、物体そのものが持つ、固有の性質ではありません。
深掘り豆知識コーナー
- ことわざの由来: 非常に古くから使われている日本のことわざで、日本人の心に深く根ざした、忍耐と不屈の精神を表します。「七」は、単なる回数ではなく「何度も」という、多さを意味する数字として使われています。そして、「八起き」と、最後に一つ多い数字を持ってくることで、「必ず、最後は立ち上がる」という、ポジティブで、力強い意志を表現しています。
- 面白雑学: 「だるま」は、禅宗の開祖である、達磨大師(だるまたいし)がモデルになっています。伝説によれば、達磨大師は、9年間もの間、壁に向かって座禅を続けた結果、手足が腐ってしまった、と言われています。だるまの、手足のない、丸い形は、この伝説を表しているのです。そして、だるまには、最初に片方の目だけを入れ、願い事が叶った時に、もう片方の目を入れる、という風習があります。これは、持ち主自身の「七転び八起き」の努力によって、願いを成就させる、という、願掛けの道具でもあるのです。
まとめ:明日から使える「知恵」
「七転び八起き」とは、単なる精神論ではありません。それは、だるまのシンプルな物理設計が示すように、「いかにして、転んでも必ず起き上がる、安定した構造を作るか」という、極めて合理的な設計思想なのです。その鍵は、低く、どっしりとした「重心」にありました。
つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは… 『転ばないための技術を磨くのではない。自らの「重心」を、どこに置くかを考えよ。強固な中心核こそが、あなたを、必ず、再び立ち上がらせるだろう』ということです。
このように、転んだ後に「起き上がる」ための心の設計は非常に重要です。
そして、そもそも「転ぶ」こと自体を、私たちはネガティブに捉えすぎる必要はないのかもしれません。もし、達人ですら転ぶことが「必然」であるとしたら? 「失敗」そのものの見方が変わる、こんなお話もあります。
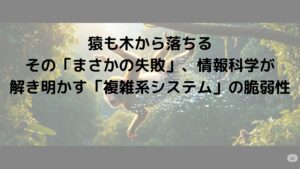
さらに視点を変え、日々の「行動」そのものを効率化する設計思想に興味はありませんか?
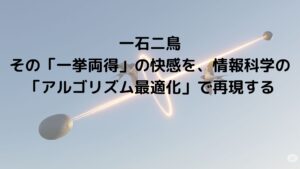
あなたの人生における「重心」、すなわち、あなたを支え、何度でも立ち直らせてくれる、最も大切なものは何ですか?
この記事では、何度、打ちのめされても、起き上がるための、「心の防御力」について、解説しました。では、その、防御力を、試す、最も、手強い「攻撃」とは、一体、どのようなものでしょうか? 「四面楚歌」ということわざが、歴史上、最も、恐ろしい「心理戦」の、実例を、教えてくれます。
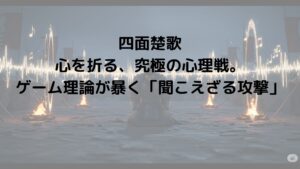
この記事では、転んだ後に「起き上がる」ための、物理的な安定構造について解説しました。では、そもそも「転びにくい」、幸運を引き寄せるような、心の状態を、科学的に作り出すことはできるのでしょうか? 「笑う」という行為が、脳内で起こす、驚くべき化学反応について、こちらの記事が教えてくれます。
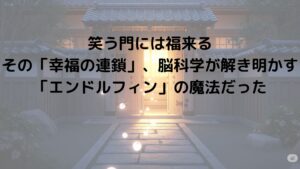
この記事では、「達人の失敗」をシステムの観点から解説しました。しかし、この現象には、達人の脳内で起きている、驚くべき「心理的なワナ」も存在します。「弘法にも筆の誤り」という、もう一つの視点はこちらです。
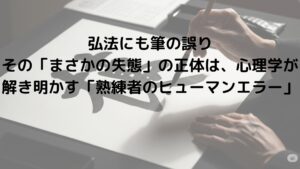
そして、そのように避けられない失敗から、力強く立ち直るための「心の構造」については、こちらの記事がヒントになるはずです。
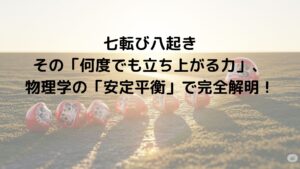
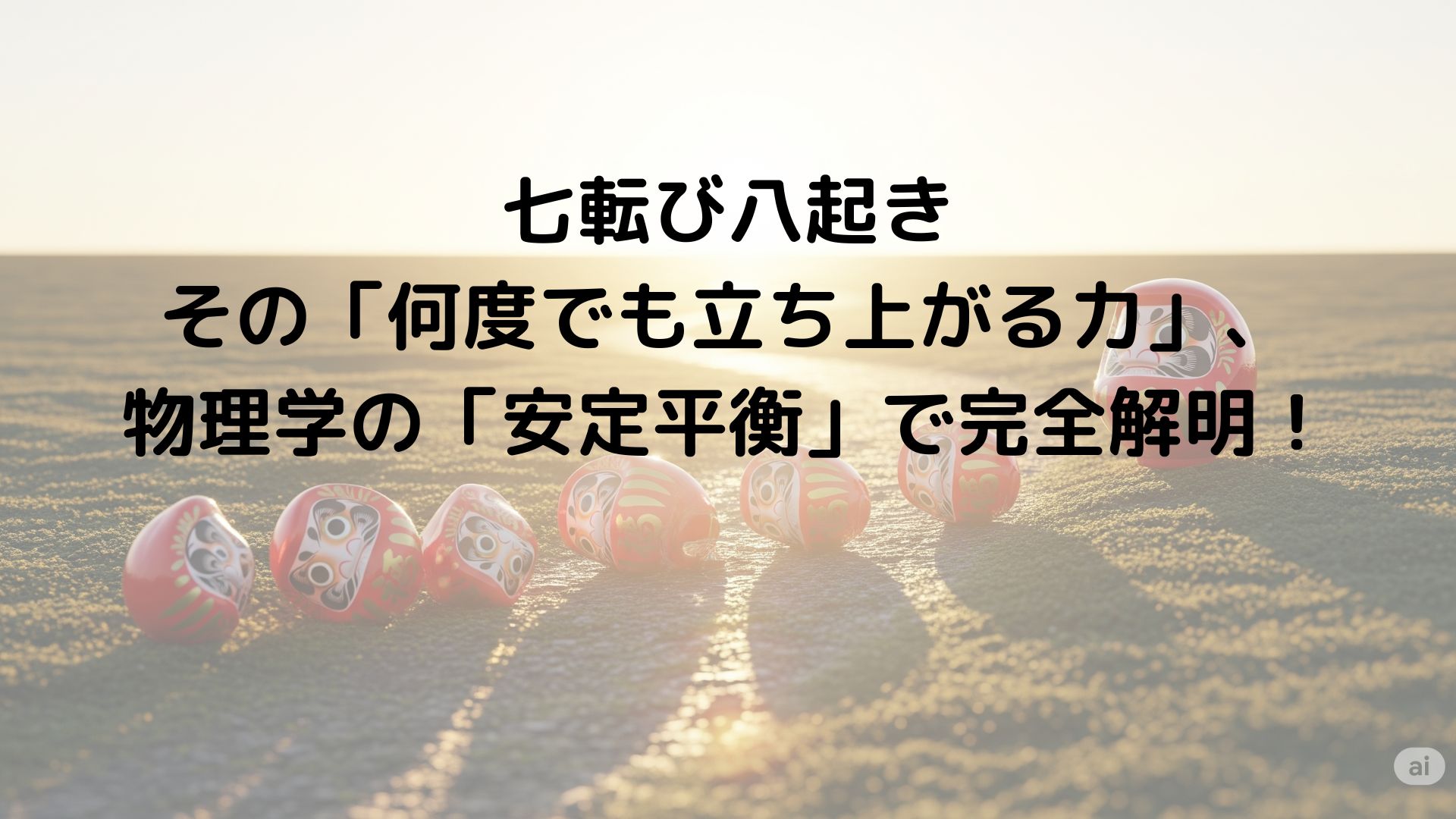
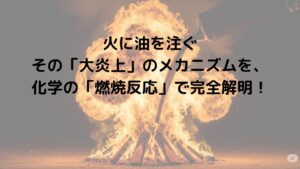
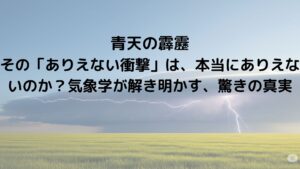
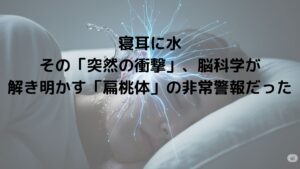
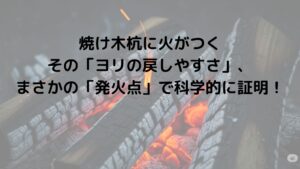
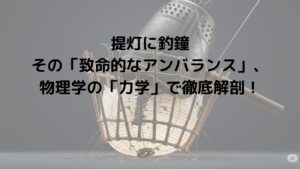
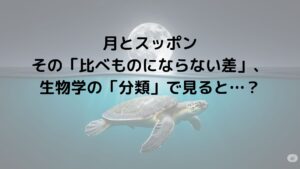
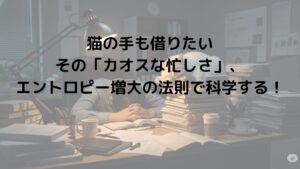
コメント