住宅ローンは家づくり最大の不安要素
「頭金は入れるべき?」「返済比率は何%なら安心?」「ネット銀行と地銀、どっちが得?」——私も契約直前まで迷いました。
本記事では、実際に契約した一次情報(借入額・金利・返済額・諸費用・審査の大変さ・繰上げ返済方針)をすべて公開。さらに、返済比率を“単独収入”と“世帯収入”の両面で比較し、頭金ゼロの考え方や地方銀行を選んだ理由も具体的に解説します。
「数字で判断したい」「同じ条件でシミュレーションしたい」という方が、そのまま自分事に置き換えられる内容にしました。
- 頭金を入れるか迷っている
- 世帯年収800万円前後で返済比率の目安を知りたい
- ネット銀行と地方銀行の違いを実例で比較したい
- 諸費用の現実的な金額感を掴みたい
この記事でわかること
- 我が家の住宅ローン条件(借入額・金利・返済額・返済回数・団信)がわかる
- 諸費用の実例(約95万円)の内訳がわかる
- 頭金ゼロでも住宅ローン控除を活かす判断軸がわかる
- 返済比率を「単独収入」と「世帯収入」で比較できる
- ネット銀行と地方銀行の意思決定プロセスがわかる
- 繰上げ返済は当面しない(投資優先)という戦略思考がわかる
住宅ローンの借入条件(我が家の実例)
■ 金融機関:地方銀行
■ 借入額:4,560万円
■ 返済期間:40年(476回)
■ 金利タイプ:当初特約期間の固定 0.35%
■ 毎月返済額:102,616円(ボーナス払いなし)
■ 団体信用生命保険:八大疾病団信
■ 連帯債務:夫 70%:妻 30%
■ 総返済額(見込み):約4,844万円
■ 総利息(見込み):約284万円
用語の超簡単補足
- 当初特約期間固定:はじめの一定期間だけ金利を固定する仕組み。終了後は金利タイプを再選択(借換え検討のタイミング)。
- 八大疾病団信:がん・急性心筋梗塞・脳卒中等に対応した団信。万一の家計リスクに備える保険。
- 連帯債務:夫婦それぞれが借入の債務者になり、持分に応じて返済責任を負う形。
頭金ゼロで組んだ理由と住宅ローン控除
結論:フルローン(頭金ゼロ)を選択
- 現金を生活の初期投資へ(家具・家電・外構・引越し後の突発費用)
- 控除のベースを確保(年末残高が多いほど“最大1%の控除額の上限”に届きやすい)
- 年末残高 ≒ 4,560万円 → 約45.6万円(上限ベース)
- 実際の還付額は「所得税+住民税(一定上限)」の範囲内。
- 家計へのキャッシュイン(初期数年)は心理的にも大きい。
頭金を入れなかった分は、家具・家電・外構などの初期投資に充てました。
実際にどんな家を建てたのか気になる方は 👉 我が家の間取り公開|35坪・グランスマート実例をどうぞ。
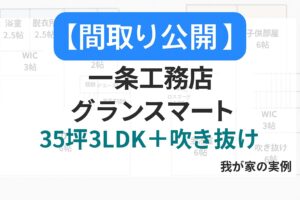
住宅ローンの返済比率を比較(単独/世帯)
- 毎月返済額:102,616円
- 私ひとりの収入(手取り約27万円) → 約38%
- 世帯年収800万円ベース(手取り約50万円前後) → 約20%
“数字の見え方”が結論を左右します。
個人ベースでは負担感が強い(38%)一方、世帯ベースでは20%で現実的。一般的に25%以下が目安と言われるため、我が家は世帯視点なら無理のない水準と判断しました。
見方 / 手取り / 返済額 / 返済比率
- 私ひとり:27万円 / 102,616円 / 約38%
- 世帯:50万円前後 / 102,616円 / 約20%
住宅ローン審査で大変だったこと(実体験と対策)
大変だった点
- 証券口座が複数:金融所得の明細整理が負担。
- 奨学金の返済残:残高証明・返済予定表の提出で手間。
- 書類の枚数:源泉徴収票、残高・取引明細、身分証、住民票、課税証明 等。
乗り切り方
- 事前に口座・証券口座を一覧化(口座名/用途/提出書類)
- クラウド保存(PDF化)で再提出に即応
- 収入合算の場合は各人の書類を色分けしてミス防止
- 奨学金等の他債務の月返済額を把握し、返済比率に反映しておく
繰上げ返済は当面せず、投資を優先する方針
- 教育費の先取り貯蓄と生活防衛資金を厚めに確保
- 余剰資金が出ても、期待リターン>住宅ローン金利なら投資を選好
- ただし、金利上昇・家計の不確実性が高まれば、繰上げ返済へ機動的にシフト
- 手元資金(生活防衛6–12か月)確保 →我が家の場合は共通の口座に300万円あり。
- 教育・大型支出の時期見通し →子供が大学に行く頃(17年〜20年後)に大学費用準備。
- 投資期待リターン vs ローン金利 →オルカン投資で長期の想定年平均4%見積もり。
- 税制(控除残年数)と団信による万一リスク低減も考慮。
現時点では繰上げ返済より投資を優先しています。実際に積立している「eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)」の実績も公開しています。
👉 詳しくは 2025年の資産公開!投資10年で資産1148万円と今後の目標 をご覧ください。
ネット銀行と地方銀行の比較と選んだ理由
- 当初特約期間の金利 0.35%が圧倒的に有利
- 窓口での相談のしやすさ/手続きの安心感
- 我が家の審査属性(共働き・連帯債務)と相性が良かった
ざっくり比較(一般論+我が家の着眼点)
- ネット銀行:金利水準は低め/手数料は個別比較必須/手続きは非対面中心
- 地方銀行:金利は個別交渉余地あり/対面サポートが手厚い/地域制度や補助の案内に強み
→ 我が家は“トータルコスト×安心感”で地銀に軍配。
住宅ローンの諸費用の内訳(実例:95万円)
内訳(実額)
- 貸付手数料:495,000円
- 火災・地震保険(5年分):183,160円
- 登記・司法書士費用:278,000円
- 合計:約95万円
ポイント
- 手数料方式(保証料ではなく一括手数料)を選択
- 保険は補償内容×期間で要比較(地震の上乗せ条件など)
- 登記は抵当権設定/所有権保存・移転等で金額が動きやすい
一般的な目安
- 諸費用は数%単位の幅があり、金融機関・商品・登記条件で上下。
- 見積は“金融機関+司法書士+保険”を別立てで把握するとズレが少ない。
金利上昇などのリスクと対策
- 金利上昇:当初固定終了前に借換え含む再検討をスケジュール化
- 病気・就業不能:八大疾病団信+就業不能保険の要否を点検
- 収入減少:家計の固定費圧縮リスト(通信・保険・サブスク・車)を事前に用意
- 教育費ピーク:中高〜大学の年度キャッシュフロー表を先に作っておく
まとめ:我が家の住宅ローンから学べること
- 頭金ゼロ×低金利×控除で、当面の返済負担はコントロール可能
- 返済比率は“単独”と“世帯”で見比べると判断がブレない
- 手数料方式を選んだことで初期コストは明確化
- 当初固定終了時は再選択の好機(借換え含め金利と手数料を総合比較)
- 繰上げ返済は“金利・リターン・流動性”の三点で動的に判断
後悔しないコツは、
- 数字を世帯視点で二重確認、
- 諸費用を別建てで把握、
- 当初固定の出口(借換え含む)を前倒しで設計。
この3つだけは、記事を閉じる前にメモしておいてください。
チェックリスト(印刷・メモ推奨)
【資金計画】
□ 頭金はいくら残すと生活が安定?(初期投資・緊急資金を優先)
□ 世帯手取りベースで返済比率を試算(目安25%以下)
□ 変動・固定・当初固定の出口戦略を決めた
【諸費用】
□ 金融機関手数料/保証料の方式と総額を把握
□ 火災・地震保険は補償範囲×免責×期間で比較
□ 登記費用の見積は司法書士に明細で依頼
【審査・実務】
□ 証券口座・他債務の一覧化/PDF化
□ 収入合算なら書類を人別に色分け
□ 当初固定終了の半年前に見直しタスクをカレンダーへ
付録:用語ミニ辞典
- 当初特約期間固定:最初の○年は固定金利。終了時に金利タイプを再選択。
- 連帯債務:夫婦双方が主たる債務者。持分に応じて返済責任。
- 団信(八大疾病):重大疾病等の状態で返済負担を軽減/免除しうる保険。
- 手数料方式/保証料方式:ローンのコスト構造。総額と繰上げ時の戻り有無も比較ポイント。
- 返済比率:毎月返済額 ÷ 手取り月収。“世帯手取り”で再計算するのが実態に近い。
付録:我が家の計算メモ(再現用)
- 返済比率(私ひとり):102,616 ÷ 270,000 ≒ 約38%
- 返済比率(世帯):102,616 ÷ 500,000 ≒ 約20%
- 初年度控除“上限ベース”:年末残高 45,600,000 × 1% ≒ 456,000円(実際の還付は税額内)
よくある質問(FAQ)
- 頭金ゼロは危険では?
-
「危険かどうか」は流動性と返済比率で決まります。世帯手取りで返済比率25%以下、かつ生活防衛資金(6〜12か月)を確保できるなら、頭金は後回しでも合理的。控除のベース確保という利点もあります。
- 返済比率は「個人」か「世帯」どちらで見る?
-
実生活に近い判断は“世帯手取り”です。個人だけで見ると過大評価になりやすいので、まず世帯手取りで25%以下を目安に。参考:我が家は個人約38%、世帯約20%。
- 保証料方式と手数料方式、どっちが得?
-
総支払額と繰上げ返済時の戻り有無で変わります。手数料方式はコストが明確、保証料方式は繰上げ時に一部戻る場合あり。各行の条件で試算して「トータル」で比較を。
- 当初特約期間が終わる時、何をすればいい?
-
半年前から準備開始が理想。①最新金利と諸費用を収集 ②借換えの事前審査 ③固定・変動・再度当初固定の3案を家計イベント表(教育費ピーク等)と照合して選択。
- 繰上げ返済と投資、どちらを優先?
-
期待リターン(税引き後)とローン金利+手数料を比較。低金利下では投資優先が合理的な場面も多いですが、金利上昇や収入不安定時は流動性重視→繰上げ返済へシフト。
- 地方銀行とネット銀行、どう選ぶ?
-
金利だけでなく「諸費用・審査難度・事務手続き負担・サポート」を総合点で評価。我が家は当初特約0.35%と対面サポートを重視して地銀を選択。
- 諸費用はいくら見ておけば安心?
-
金融機関手数料(または保証料)、登記、火災・地震保険で幅があります。目安は物件価格の数%と言われますが、我が家の実例は約95万円。見積は「金融機関/司法書士/保険」を別立てで取得するとズレが少ないです。
- 団信(八大疾病)は入ったほうがいい?
-
収入の安定性と貯蓄規模で判断。万一時の家計破綻リスクを大きく下げられるため、共働き世帯でも子育て期は優先度が高め。就業不能保険の要否も合わせて点検を。
- 返済比率が25%を少し超えるが、買ってもいい?
-
“恒常収入”で再計算し、家計の固定費(通信・保険・サブスク・車)を圧縮して25%以下に落ちるかを先に検証。落ちない場合は頭金の追加や物件価格の調整を検討。
最後に
本記事はあくまで我が家の一次情報と判断基準です。条件や家計構造が違えば最適解も変わります。
ただし、「世帯視点での返済比率」「諸費用の見える化」「当初固定の出口戦略」の3点は、どの家庭にも有効な“転用可能なフレーム”です。あなたの資金計画づくりに、丸ごと使ってください。
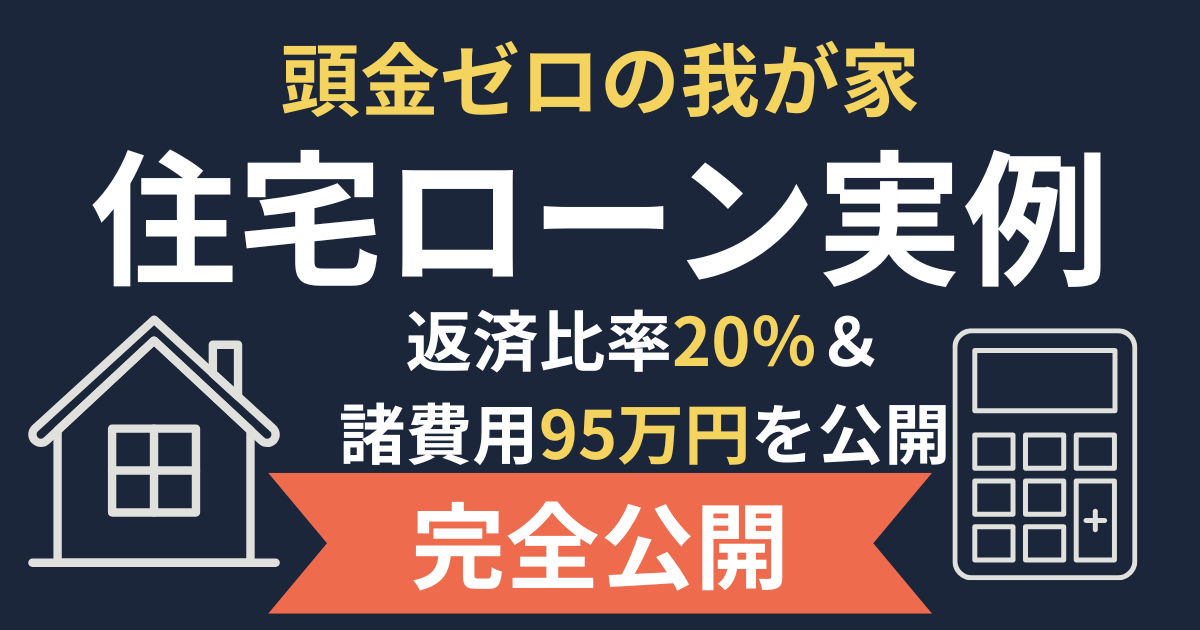



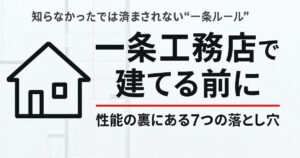

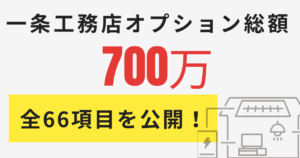


コメント