はじめに
私自身、第一子の誕生にあわせて1年間の育休を取得しました。
当時は「収入はどうなるの?」「復帰したらどんな部署になるの?」「夜勤はどう再開するの?」と、不安と期待が入り混じっていました。
そして実際に復帰してみると、配置換えによる人間関係のリセット、夜勤シフトの復活による給与の増減、育休を取ったことへの周囲の評価や空気感など、想像以上に変化と学びがありました。
- 復帰後の部署異動と人間関係のリセット
- 夜勤再開の流れと給与の変化
- キャリアや昇進への影響
- 同僚や上司からの評価、ポジティブ/ネガティブな声
これから育休を検討している看護師の方や、同じように復帰を控えて不安を抱えている方にとって、少しでも参考になれば幸いです。
復帰後は元の部署に戻れず
復帰後、私は元いた部署に戻ることはできず、新しい部署への異動となりました。
長く一緒に働いてきた仲間がいない環境に入るのは、思っていた以上に大きなストレスでした。
もちろん、人間関係はリセットされるので、一から築き直す必要があります。
幸いにも、以前から顔見知りの同僚がいてくれたことで「少しでも頼れる人がいる」という安心感はありました。
ただ、その同僚が不在の時は状況が一変します。
まだ名前も覚えきれていないスタッフが多く、「この場面では誰に声をかけるべきか」、「どの先輩に確認すればいいか」が分からず、業務の中で立ち止まってしまうこともしばしば。
慣れない人間関係と新しい環境に、常に緊張しながら過ごしていたのを覚えています。
「育休を取った人」という目線
復帰後は、周囲から「育休を取った人」という特別な目で見られる場面が多々ありました。
良い反応もあれば、正直耳が痛いような意見もあり、両方を受け止める必要がありました。
良い反応
- 「奥さん助かっただろうね」
- 「1年間は前例がないからすごいね」
- 「後輩たちも育休を取りやすくなった」
こうした声は素直にうれしく感じました。特に「後輩たちも育休を取りやすくなった」という言葉は、自分の選択が周囲の働き方にも影響を与えたと実感できる瞬間でした。
悪い反応
- 「男が育休を取ったところで何もしないだろ」
- 「かえって奥さんの負担が増えるんじゃない?」
- 「寝返り前の赤ちゃんはよく寝るから、ただ抱っこしてるだけで楽だよね」
こうした意見には、まだまだ「男性育休=楽をしている」という偏見や誤解が根強いことを痛感しました。
👉 しかし、実際に経験してみると、育休は決して「楽」ではありません。
- 真夜中の授乳や抱っこでほとんど眠れない
- 赤ちゃんの昼夜逆転で大人の生活リズムが崩れる
- 外出もままならず、孤独感や閉塞感に悩む
- 家事・育児の分担をめぐる夫婦間のすり合わせ
こうした大変さは、実際に育休を取ってみなければ分からない部分だと思います。
周囲からの声に揺さぶられることもありましたが、「家庭を優先する」という自分の選択を正解にするのは自分自身だ」と割り切るようにしていました。
夜勤復帰と給与の変化
復帰後のシフトについては、希望を聞かれることはなく、まずは1ヶ月間は日勤のみ。
その後は段階的ではなく、一気に夜勤フル勤務へと移行しました。
給与面で見ると、夜勤手当が戻ることで月に約3万円前後の差が出ました。
日勤だけだとどうしても手取りは減りますが、夜勤に復帰すれば一気に戻るので、この差は数字としてはかなり大きいと感じます。
ただし、ここで強調したいのは、育休中であっても昇給はちゃんと反映されるという点です。
また夜勤手当は「回数に応じて変動する臨時収入」のようなものであり、安定的に得られる基本給とは性質が違います。
私自身は、そもそも生活設計の段階から「夜勤手当を当てにする家計管理」をしていません。
夜勤に入ればプラスになるけれど、ゼロでも赤字にならないようにやりくりを組んでいます。
👉 だからこそ、夜勤手当がある月は「ありがたい臨時ボーナス」として受け止めることができ、精神的にも安定して働けています。
逆に「手当がないと生活が成り立たない」という状況だと、復帰後のシフトや収入の変化に大きく振り回されてしまうかもしれません。
キャリアや昇進への影響
私はもともとキャリアアップや昇進に強い興味がなかったため、育休を取得したことでのマイナス影響は特に感じませんでした。
復帰後も戦力外扱いされることはなく、与えられた業務を通常通りこなすことができました。
ただし、子どもが保育園に通い始める時期と重なったため、発熱や体調不良で病休をもらう場面はどうしても増えました。
そのたびに「申し訳ない」と感じる気持ちはありましたが、同僚からすれば「次は自分の番」ということもあるはずです。
また、昇進や役職に就くことを強く望まなかったからこそ、育休取得によるキャリアの停滞を気にせずに済んだ部分もあります。
逆に「管理職を目指している人」にとっては、育休が評価やチャンスに影響する場合もあるかもしれません。
👉 つまり、育休によるキャリアへの影響は「自分がどの働き方を望むか」で大きく変わるのだと思います。
周囲の評価・空気感
復帰後、同僚からかけられた言葉の中には、励まされるものもあれば、少し引っかかるものもありました。
🟢 ポジティブな声
- 「家庭を大事にして偉いね」
- 「奥さんも助かっただろうね」
こうした言葉をかけてもらえると、素直に「育休を取って良かった」と思えました。特に「家庭を大事にしている」と評価してもらえたのは、男性看護師としては珍しい選択だったこともあり、自分の決断に自信を持てるきっかけになりました。
🔵 ネガティブな声
- 「また休むんじゃないの?」
- 「今は制度が充実してていいね」
一見すると軽い冗談のようにも聞こえますが、裏には「戦力が減る」「自分たちにはなかった制度」という感情が含まれていると感じることもありました。
そんな時、私は笑顔で「二人目ができたらまた1年休みます!」と返すようにしていました。
本音を言えば内心モヤッとすることもありましたが、自分の選択を後ろめたく思わないことが一番大切だと思ったからです。
周囲の声はポジティブ・ネガティブどちらもありますが、最後に大事なのは「自分のスタンスをどう貫くか」。
制度を利用するのは権利であり、遠慮する必要はありません。
むしろ、あなたが堂々と活用することで、次に続く後輩たちの道が広がります。
保育園と家庭の両立
我が家では、妻に時短勤務を取ってもらい、保育園の送迎は妻が担当しています。
その代わりに、家事は基本的に私の担当と役割分担を決めています。
夜勤のある働き方をしている以上、どうしても「妻がワンオペ育児になる日」が発生してしまいます。
その負担を少しでも軽くするために、私は「妻に家事は一切しなくていい」と伝え、夜勤の前後で家事をまとめてこなすスタイルをとっています。
- 夜勤前にご飯を作っておく日もある
- どうしても余裕がない日はレトルトや冷凍食品に頼る
- 子どもの食事も、忙しい日はレトルトやベビーフードを使って割り切る
👉 育休復帰後は仕事・保育園・家庭の三つ巴で忙しくなりますが、夫婦で「ここは自分」「ここは任せる」と線引きを明確にすることで、互いに無理のない生活リズムを維持できていると感じます。
まとめ
育休明けの看護師復帰は、部署異動や人間関係のリセット、夜勤再開、周囲からの評価など、想像以上に多くの変化があります。
- 部署異動で人間関係はゼロから。不安もあったが、新しい自分を見せるチャンスにもなった。
- 「育休を取った人」という目線は賛否両論。最終的に大切なのは「家庭を優先する」という自分の軸。
- 夜勤復帰で給与は約3万円前後の差。昇給は育休中も反映。夜勤手当に依存しない家計設計でブレない。
- キャリアの大きなマイナスはなし。子の病休は「お互い様」で支え合う。
- 家庭は役割分担がカギ。送迎は妻、家事は夫。完璧を求めず時短術を活用。
👉 育休復帰は決して楽ではありませんが、工夫と割り切り次第で「家庭も仕事も大切にできる働き方」を実現できます。
そして何より、育休は「権利」であり、遠慮せずに前向きに使うべき制度です。
🟢 「あなたも育休を取っていいし、取るべきだ」ということ。
🟢 そして妻の立場からも、「夫に育休を取ってほしい」と安心して伝えてほしいということ。
仕事は代わりがいても、家族の時間の代わりはありません。
育休はキャリアを止めるものではなく、むしろこれからの働き方や家庭の在り方を見直す大きなチャンスです。
どうか一人でも多くの男性が育休を前向きに選び、家族の時間を大切にしてほしいと願っています。

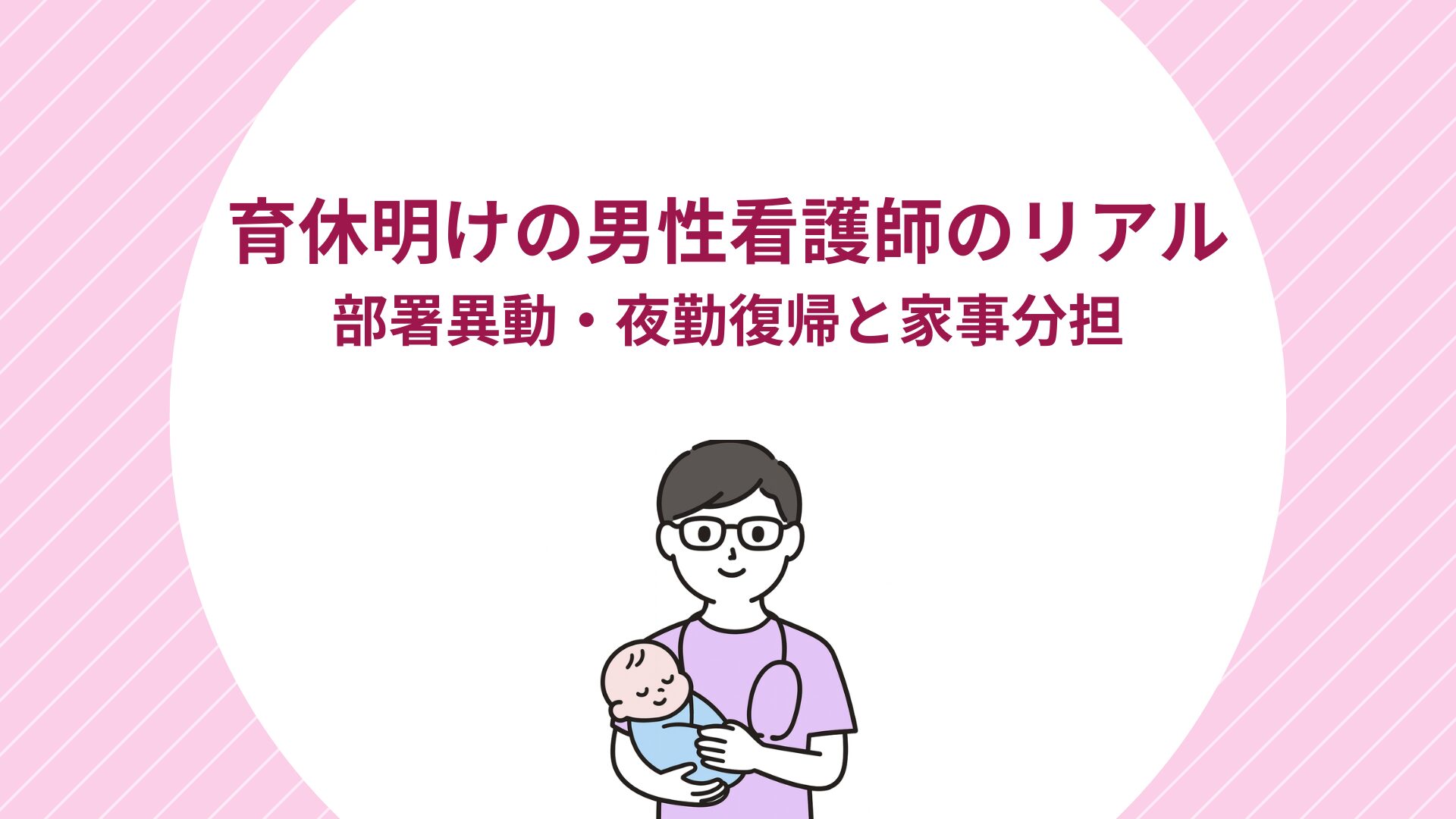


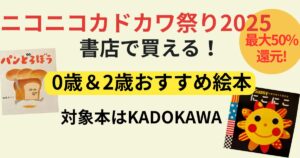
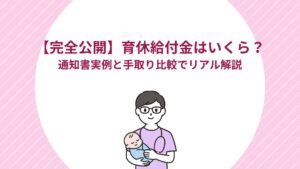
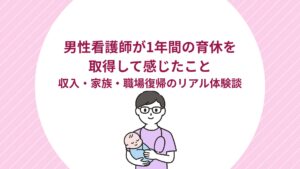
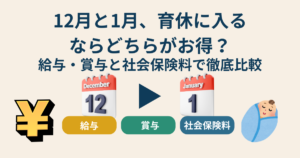
コメント