はじめに
こんにちは、まもるです。
私は男性看護師として10年ほど働いてきましたが、第一子誕生の際に「夫婦で1年間の育児休業を取る」という決断をしました。
看護師という仕事柄、夜勤や不規則勤務も多く、正直「家庭と仕事の両立」に自信がありませんでした。
だからこそ思い切って1年育休を取り、妻と一緒に子育てをしてみようと考えたのです。
この記事では、実際に1年間の育休を経験して感じたことを正直に書いていきます。
これから育休を検討している方の参考になれば嬉しいです。
男性看護師が育休前に感じていた不安と期待
正直に言うと、不安もありましたが、それ以上に「楽しみ」の方が大きかったです。
・職場の理解は得られるのか?
・1年間現場を離れてブランクができてしまわないか?
・給与がなくなり、育休給付金だけでやっていけるのか?
こうした不安はありつつも、「夫婦で一緒に子どもの成長を見守れる」「仕事に追われず、家族に集中できる」という期待感の方が強く、家族にとってかけがえのない時間になるだろうとワクワクしていました。
1年間の育休で得られたこと・感じたこと
夫婦で育児を分担できる安心感
一番大きかったのは、育児を2人で分担できる安心感です。
ワンオペになる時間がほとんどなく、夜泣きや日中の世話も協力しながら交代で対応できました。
 妻
妻私がやるから、少し休んで



今日はお願い、明日は代わるね
そんな声かけが自然にできるのは、夫婦同時に育休を取ったからこそだと実感しました。
また、完全母乳の場合でも搾乳やミルク併用により、男性でも十分に育児へ関われます。育休中は「やることがない」どころか、関われることがたくさんありました。
子どもの成長を一緒に見守れる喜び
毎日のように新しい表情や仕草を見せてくれる子ども。
寝返り、初めてのつかまり立ち、新生児微笑ではない“声を出して笑う”瞬間——。
夜勤を続けていたら見逃していたかもしれない小さな成長を、夫婦で共有できたのは本当に幸せでした。
さらに、子どもが体調を崩したときに二人で看病できたことも大きな安心感につながりました。片方が病院に連れて行き、もう片方が家事を担う。共働きだからこそ「育休を取っていなければ対応できなかった」と強く実感しました。
男性育休を経験して変わった価値観
もともと私は「家族が最優先で、昇進には興味がない」という価値観でした。
そのため育休を取ることに抵抗はほとんどなく、「当然の選択」という感覚でした。
とはいえ、看護師の仕事は責任と負担が大きいのも事実。1年家庭に専念してみると、「無理をしてまで働く必要はない」「家族と過ごす時間はお金には代えられない」という実感がより強まりました。
育休中に直面した課題と工夫
家計管理と給付金の難しさ
育休中の家計では、収入減は避けられません。
育休給付金はあるものの給与の約7割程度で、ボーナスも大幅に減ります。さらに支給は後払いで、申請から1〜2か月遅れて入金されることもありました。
育休給付金のキャッシュフロー
・給付金は2か月ごとの後払いが基本。最初の入金までラグがあるので要注意。
・生活費2〜3か月分の現金を用意しておくと安心。
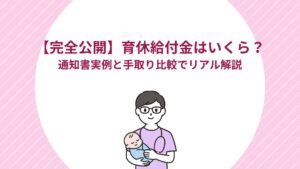
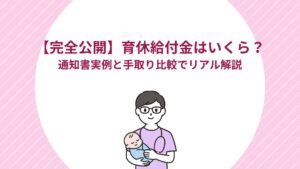
特に「ふるさと納税」は、課税所得が下がるぶん上限見極めが難しく、安全策として少額にとどめました。前年所得ベースの6〜8割を目安にしておけば安心です。
固定費(格安SIM・保険など)は育休前に見直し済み。住まいは当時アパートで電気代対策は限定的でしたが、子どもの体調を最優先にエアコン温度をやや高めに設定しました。
日常支出は外食を減らして自炊中心(料理は私が担当)。おむつ・ミルクはまとめ買い+ポイント還元、「ウェル活」を主に活用。隙間時間のポイ活でウェル活の原資も確保しました。
職場復帰で苦労したことと対策
復帰ではいくつかの壁がありました。希望とは違う部署配属となり、人間関係はリセット。私はもともと人の顔と名前を覚えるのが苦手で、新しい同僚や患者さんを覚えるのに苦労しました。
マニュアルやシステムの大きな変更はなかったものの、病棟独自ルールが多く、勝手が違って慣れるまで時間が必要でした。
勤務形態も、復帰直後は夜勤なしの日勤のみ。両立には助かった一方、夜勤手当がないぶん給与は育休中とほぼ同等で、「看護師の給与は夜勤手当あってこそ」という現実も再認識しました。
復帰前チェックリスト
□ 夜勤再開は段階的に上司と調整(日勤→準夜→深夜)
□ 新病棟のルール・略語リストを事前にメモ化
□ 送迎・病児対応の代替プラン(祖父母/病児保育/ベビーシッター)
□ 配置換えを想定して通勤・シフトを再計算
□ 夜勤なし月収を基準にキャッシュフローを再試算
男性育休に対する周囲の反応と感じたこと
男性育休は社会的にはまだ浸透しておらず、誤解や偏見も多く感じました。
・「1年も休んで職場に迷惑かけないの?」
→ 家族が第一。国や職場が整えた制度を利用するのは当然だと思います。
・「育休中って毎日遊んでるんでしょ?」
→ 実際は夜泣きや離乳食で24時間フル稼働。ただ一方で、子どもが寝ている間に妻とテレビを見たり、家族で買い物に出かけたり、かけがえのない時間も確かにありました。
・「男が家にいてもやることないでしょ?」
→ 授乳以外にもおむつ替え、抱っこ、寝かしつけ、家事などやれることは無数。私は産前から家事全般を担っていたので自然に両立できました。
・「出世に響くよ」
→ 昇進に興味がない私には的外れでしたが、まだ“男は働いて一人前”という価値観は根強いと感じます。大事なのは周りに流されず、自分の価値観を大切にすること。
・「奥さんが大変だから代わりに休んだんでしょ?」
→ 私自身の意志で取得しました。役割分担はあっても「一緒に育児をする」という意識に変わりはありません。
これから育休を取る男性へのアドバイス
① 家計シミュレーションは必須。給付金は給与の7割程度+後払い。現金クッションを必ず準備。
② 家事・育児分担は事前に言語化。「夜泣きは交代制」など明文化しておくと安心。
③ 復帰後の働き方を夫婦で設計。時短・夜勤調整・送迎分担を逆算で決めておく。
④ 完璧を求めず楽しむ。「今日も一緒に過ごせた」と思えることが最大の価値。
まとめ|男性看護師が1年間の育休を取って気づいたこと
1年間の育休は経済的に楽ではありませんでした。
それでも、家族で過ごした時間はどんなお金にも代えられない価値がありました。
男性看護師として育休を取ったことで、仕事やキャリア観が変わり、人生の優先順位を「家族第一」と再確認するきっかけになりました。
迷っている方へ自信を持って伝えたいです。



取れるなら、ぜひ育休を取った方がいい
不安はあっても、その一歩で得られるものは想像以上に大きいはず。
家族と過ごした濃密な時間は、一生の財産になります。

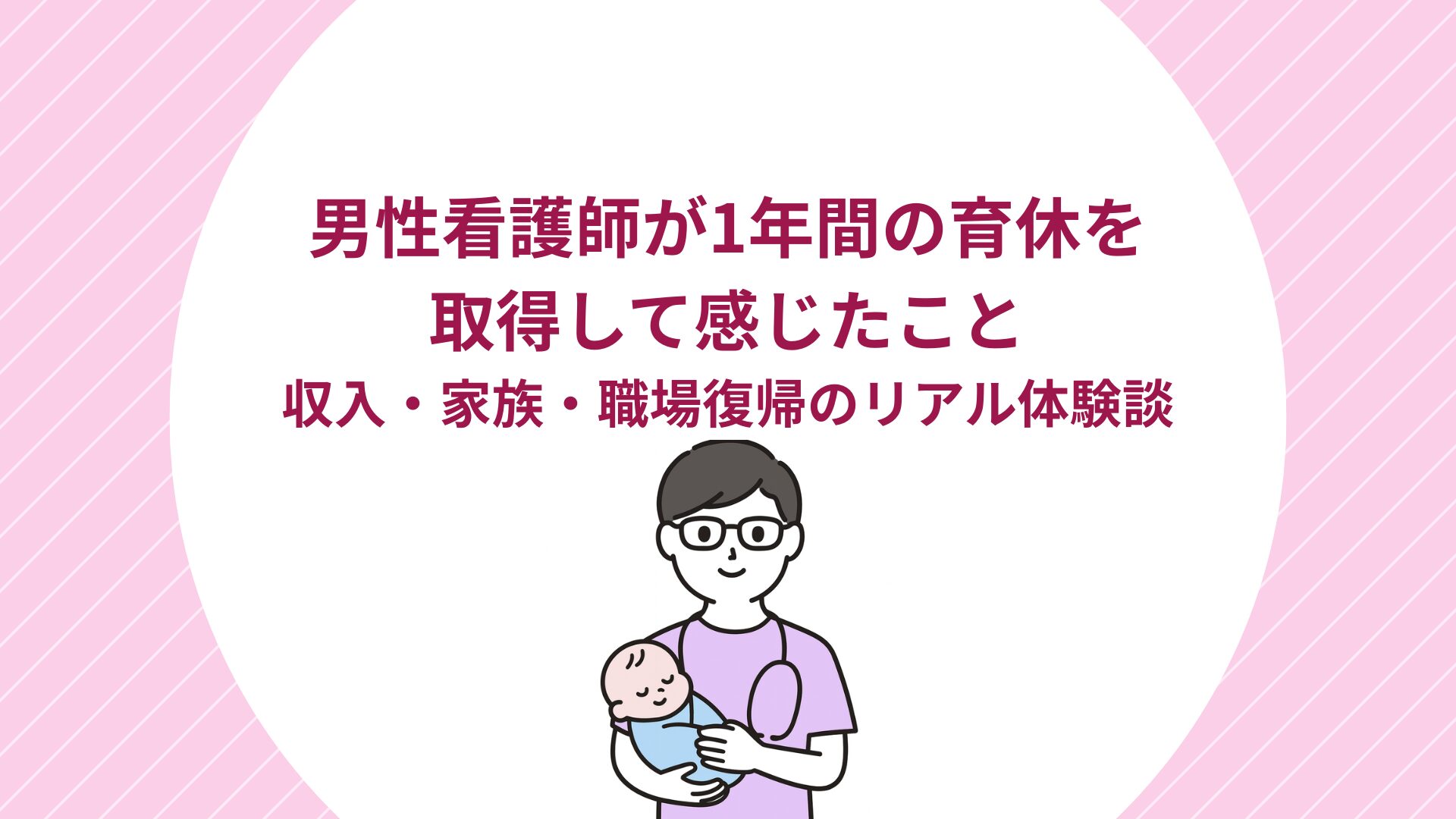


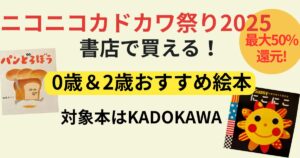
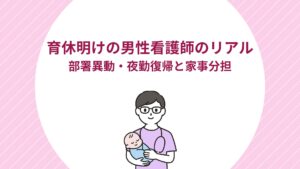
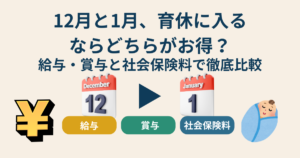
コメント